離婚時の年金分割
- 導入の背景
- 法改正前の取扱いと法改正後の年金分割の相違
- 離婚時年金分割の2つの取扱い
- 2007年4月施行の離婚時年金分割(合意分割)について
- 2008年4月施行の第3号被保険者期間の年金分割(3号分割)について
1.導入の背景
厚生年金保険法の改正は、これまで、給付と負担の適正化、高年齢者の雇用機会拡大支援、次世代育成支援など様々な観点からの施策が講じられてきたが、離婚時の年金分割は、「女性と年金」という観点から導入されたものである。
具体的には、中高年齢者等の比較的婚姻期間の長い夫婦の離婚件数が、近年、増加してきている中で、現役時代の男女の賃金水準および雇用の格差などを背景として、離婚後の夫婦双方の年金受給額に大きな差が生じ、高齢期で離婚した場合の女性の年金額(所得水準)が低いという問題に対する対応策として導入されたものである。
1985年改正で、基礎年金の導入と同時に実施された第3号被保険者制度により、収入がない被扶養者も含めて皆年金制度が確立された。これにより、1階部分の基礎年金は、個人単位の給付となっており、基礎年金については、被扶養者である専業主婦も含めて女性の年金受給権が確立した。
2004年年金改正時において、被扶養配偶者のいる被保険者が負担した保険料は共同して負担したものであることを基本的認識とし、離婚した場合に、婚姻期間の厚生年金の計算の元となる保険料納付記録(標準報酬)を分割できる「離婚時の年金分割」制度が創設された。離婚時の厚生年金記録を分割できる「離婚時年金分割」(いわゆる「合意分割」)は2007年4月施行、離婚時の「第3号被保険者期間の年金分割」(いわゆる「3号分割」)は2008年4月に施行された。なお、基礎年金については離婚分割の対象とはならず、離婚分割の対象となるのは、厚生年金の報酬比例部分のみである。
2.法改正前の取扱いと法改正後の年金分割の相違
2007年4月以前の法改正以前でも、裁判により離婚時の年金分割は可能であったが、あくまで、元夫の年金の一部を元妻が間接的に受け取る形であり、また、元夫の死亡により受け取れなくなる可能性もあった。
厚生年金保険法改正による離婚時年金分割施行後は、分割された年金は直接、国から元妻に支給され、元夫の死亡後も受給できるようになった。
(注)本コラムでは、便宜的に、年金分割による出し手(法律上「第1号改定者」という)を「元夫」、年金分割による受け手(法律上「第2号改定者」という)を「元妻」と表記しています。
3.離婚時年金分割の2つの取扱い
年金分割の方法は、2008年4月1日以降の期間について、元妻(配偶者)が第3号被保険者か否かにより異なる取扱いとなる。
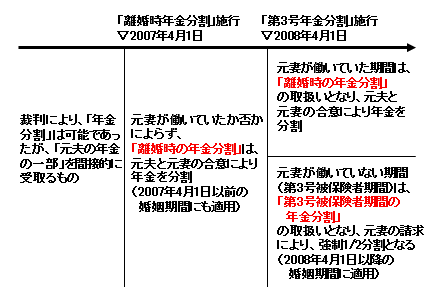
以下、2007年4月施行の「離婚時年金分割(合意分割)」と、2008年4月施行の「第3号被保険者期間の年金分割(3号分割)」に分けて解説する。
4.2007年4月施行の離婚時年金分割(合意分割)について
- (1)2007年4月1日以降に成立した離婚について、離婚時の当事者間の合意または離婚当事者の年金分割を受ける人(第2号改定者)からの請求による家庭裁判所の決定により、婚姻期間中(2007年4月以前の婚姻期間を含む)の厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬)を一定の按分割合により分割することができる。
- (2)按分割合(法律上は、二人の厚生年金の保険料納付記録の合計額のうち、分割を受ける人の保険料納付記録の持分をいう)は5割が上限。
- (3)分割を受けた元妻(第2号改定者)は、標準報酬累計が増加し、自分自身の厚生年金として、受給資格(老齢・障害)に応じた年金を受給できる。
- (4)当該年金は、元妻の老齢年金の受給資格に達した時から支給され、元夫(第1号改定者)の生死によらず、元妻の厚生年金として支給される。
- (5)年金分割を受けた元妻が死亡した場合には、分割部分にかかる遺族厚生年金が元妻の遺族に支給される。
- (6)離婚時年金分割の請求を行う際、元妻の対象期間に第3号年金分割(後述)の対象となる期間(2008年4月1日以降の第3号被保険者期間)が含まれる場合は、離婚時年金分割の請求があった時点で、同時に、第3号年金分割にかかる請求があったものとみなされる。
離婚時年金分割の請求期限は、従来、民法における離婚時の財産分与請求権の除斥期間(2年)に合わせて、離婚をした日の翌日から起算して2年以内とされていた。 - (7)しかし、2024年の第213回通常国会で成立した「民法等の一部を改正する法律」により、財産分与請求権の除斥期間は、離婚前後の事情により2年以内に請求できず経済的に困窮する事例があることから、債権一般の消滅時効期間を踏まえ、2年から5年に延長された(2024年5月24日公布、施行日は公布の日から起算して2年を超えない範囲内で政令により定める日)。
この改正に伴い、参議院法務委員会の附帯決議では「離婚時の年金分割の請求期限(現行2年)についても、財産分与と同様に5年へ延長することを早急に検討すべき」とされ、検討が進められてきた。その結果、2025年に公布された「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」により、離婚時年金分割の請求期限は2年から5年に延長され、2026年4月1日から施行される。ただし、2026年3月31日までに離婚した場合は、現行の2年が適用されるという経過措置が設けられた。
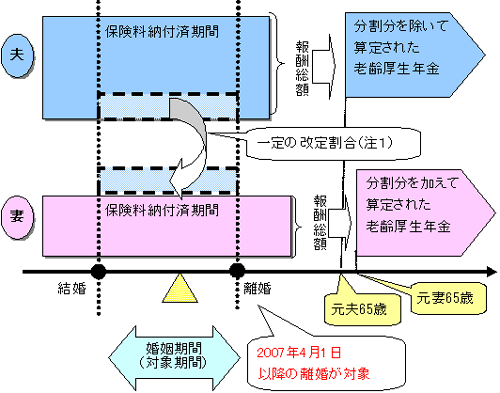
(注)
- (1)改定割合とは、分割の結果、第2号改定者の対象期間標準報酬総額の持分が、指定された按分割合どおりになる値として厚生労働省令で定められる値。
- (2)元妻の2008年4月1日以前の婚姻期間に、第3号被保険者期間がある場合は、当該期間の元妻の報酬総額はゼロとして、按分割合を計算する。
5.2008年4月施行の第3号被保険者期間の年金分割(3号分割)について
- (1)被扶養配偶者(第3号被保険者)を有する第2号被保険者が負担した保険料は、夫婦が共同して負担したものであるという基本認識が法律上、明記された。
- (2)当該夫婦が離婚した場合、2008年4月1日以降の被扶養配偶者であった期間(第3号被保険者期間)の元夫の厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬)の一律2分の1が、元妻(元被扶養配偶者)からの請求により分割される。
- (3)元夫(法律上、特定被保険者という)の同意は不要であり、前述の離婚時年金分割(合意分割)とは取扱いが異なる。
- (4)分割を受けた元妻は、自分自身の厚生年金として、受給資格(老齢・障害)に応じた年金を受給できる。
- (5)当該年金は、元妻の老齢年金の受給資格に達した時から支給され、元夫(特定被保険者)の生死によらず、元妻の厚生年金として支給される。
- (6)元妻は、厚生年金の被保険者ではないが、第3号年金分割により、「被扶養配偶者みなし被保険者期間」を有する者として、元妻が死亡した場合には、分割部分にかかる遺族厚生年金が支給される。
- (7)離婚時年金分割の請求を行う際、元妻の対象期間に第3号年金分割の対象となる期間(2008年4月1日以降の第3号被保険者期間)が含まれる場合は、離婚時年金分割の請求があった時点で、同時に、第3号年金分割にかかる請求があったものとみなされる。