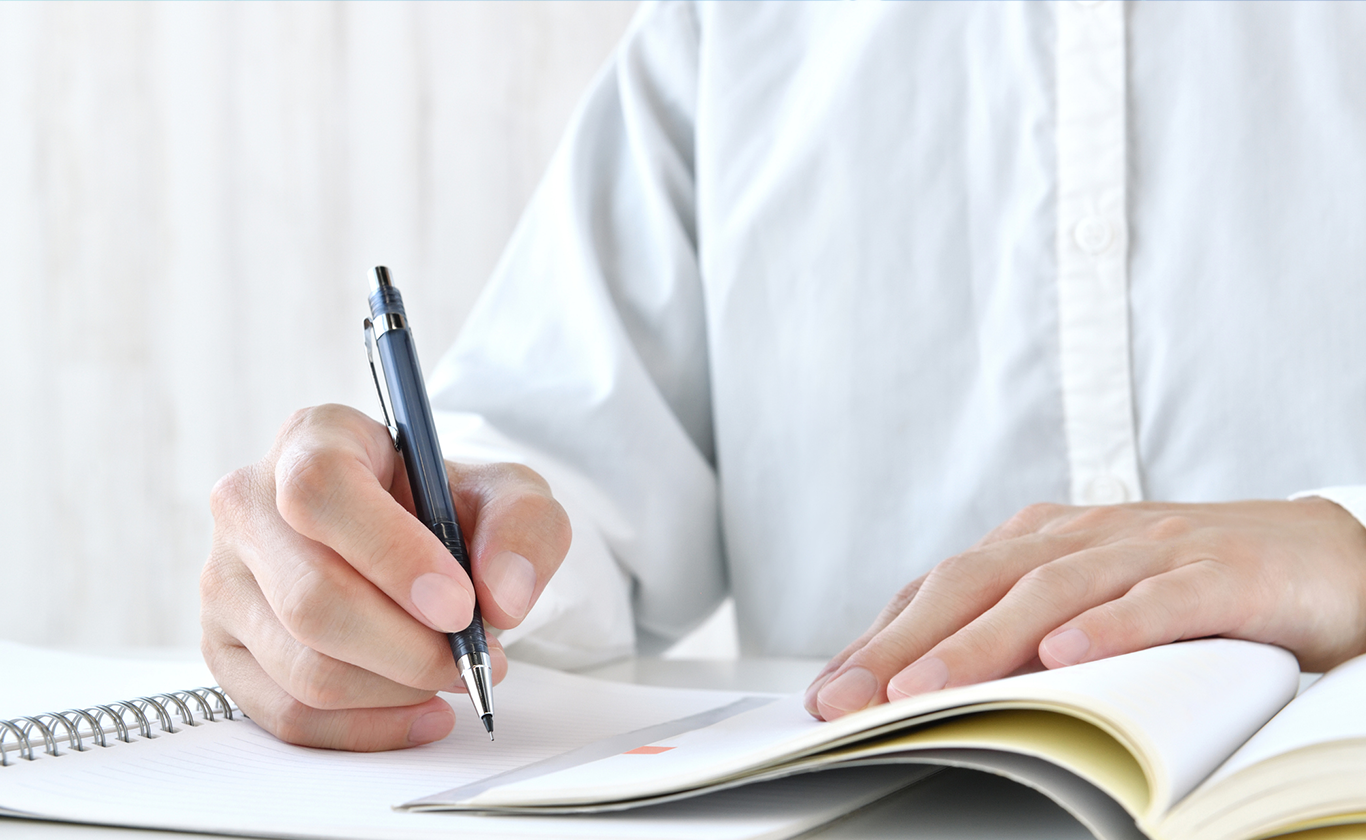誰もが等しく学べる社会を実現する。
「信託の機能を活用したサステナブルな給付型奨学金」
私は新規事業を扱うフロンティア事業開発部で、地方の再生エネルギーへの投資事業などを手掛けてきました。故郷の熊本県において、2016年の震災で被災した家族や友人が苦労している姿や復興に向けて懸命に立ち上がろうとしている姿を目の当たりにし、金融で地方創生をサポートしたいと社内のキャリアチャレンジ制度で手を挙げ、2020年に異動してきたことがきっかけです。
中尾さんと同じチームで、配当の一部を寄附に還元できる運用商品など「日本の金融×教育分野」の発展に貢献する新商品を開発しています。
もともとは他部署にいた入社3年目の頃、社内の新商品提案制度で今回のサステナブル奨学金の原型となるような奨学金制度を応募しました。学生時代は教員志望だったこともあり、教育機会の格差や奨学金の返済難などの社会課題の解決に向け、信託の機能を活用した寄附型奨学金ができないかと考えたのです。そこで社長賞を受賞することができ、今の部署に配属された後、本格的に検討を開始しました。
当時、私は審査する側でした。私も返済型奨学金を利用していたのでアイデアには共感しましたが、当時は奨学金をどのように募集・給付していくのかといったスキームが不透明でした。その頃の奨学金と言えば、大学の学生支援課のポスターくらいしか情報を得ることができなかったからです。しかし、1年ほど前から平野さんと一緒に実現の可能性を模索する中で、国内最大の奨学金プラットフォームを運営するベンチャー企業のガクシーさんと協業する道筋が開け、いろいろな要素が噛み合ってきたことから、「今しかない!」と急ピッチで開発を進めました。
担当者は2人だけなので、主に私が社内外にどうアイデアを打ち出していくかといった戦略面を担い、平野さんは寄附先候補の当たりをつけてヒアリングを行うといった分業制を採りました。そこでは私たちの対照的なキャラクターがうまく機能したように思います。私は割と冷静な性格ですが平野さんは熱意を全面に打ち出すタイプ、お客さまの心をしっかり掴んで離さないことが心強いです。
結果的に、半年ほどでローンチすることができました。通常1〜2年度かかるところ、これは異例の速さです。
当初は社内で完結するスキームを想定していたので、奨学生の募集方法や奨学金の給付を行う上での事務リスクなど、プラットフォームを構築する上での課題が山積みの状態でした。社内の他部署や外部の方々と意見交換をする中でガクシーさんを紹介され、オープンイノベーションによる実現の道が一気に開けたんです。ガクシーさんには現時点で約30万人の学生が登録しています。奨学金に関する事務のノウハウや個々の学生にアクセスするチャンネルを持つガクシーさんとの協業が、今回のスキームのポイントになりました。

国内最大の奨学金プラットフォーム。教育機関や財団などに代わって、
応募者の受付から選考、支給まで、奨学金業務を一元管理する。
「奨学金ファンドの組成で持続的な給付を可能に」

ガクシーさんのウェブサイト「ガクシーAgent」で学生の募集や給付手続きを行い、当社は一般社団法人を設立して奨学金ファンドを運営します。個人のお客さまや企業から寄附を集め、当社が信託報酬をいただいて運用を受託する形です。資金の目標額は1,000億円に設定しました。一定額を超えて寄附した企業には企業奨学金のようなものを作って、その企業が希望する属性の学生に給付するといった柔軟な運用も考えています。
奨学金ファンドの最大の特徴は、運用によって持続的な給付が可能になることです。個人の支援者の方なら「地方受験生応援奨学金」や「1人親家庭応援奨学金」といった選択肢が用意され対象となる学生の属性を指定できますから、より手触り感のある支援が可能になります。支援する企業のメリットとしては、サステナビリティ活動として対外的にアピールでき、奨学金を通して多くの学生と接点を持てることが挙げられます。目下、寄附者や拠出者を募集中ですが、おかげさまで現時点で100件近い反響をいただいています。
当初は個人の方が多いだろうと考えていましたが、予想以上に企業からの反響が大きく、驚いています。企業の社会的責任が求められる中、各企業の経営層の方からも高い関心をお寄せいただいております。このまま順調に推移していけば、ファンド組成が実現できるのではないかと考えています。日本のお客さまには「様子を見てから」という方も少なくないので、運用サイドとしてはスタートダッシュが肝心で、初年度からしっかり結果を出していく必要があります。
「本業を通じて社会課題を解決する仕組みを作る」

私はこのファンドがいずれアメリカの有名大学が運営しているような巨大な奨学金ファンドに成長してくれるといいなと思っています。あくまで、私個人の夢ですが。
寄附金の使途は、奨学金に限らず産業育成やインフラの補修などいろいろありますよね。将来的にはガクシーさん以外のパートナーも取り込んで、幅広い分野を対象にしていけば面白そうです。運用も株式や債券に限定せず、もっとアグレッシブに、たとえば社会インフラに投資してもいいかもしれません。さまざまな選択肢があるように思います。
奨学金ファンドもそうですが、私には新規事業開発とサステナビリティの推進をしていく上で常に意識していることがあります。それは、「本業を通じて社会課題を解決するような仕組み」を増やしていくことです。サステナブルな社会課題の解決のためには、当社のような営利企業には、ボランティアだけでなく、組織を継続させ事業を発展させることを通じて利益を上げ続けると同時に、課題解決に貢献するビジネスモデルの構築が求められているのではないでしょうか。
平野さんが今言った「本業を通じて社会課題を解決するような仕組み」については、よく2人でも話しますし、私自身も常に頭に置いています。最初に地方創生に携わりたくてこの部署に異動してきたと言いましたが、現在は特定の分野よりも当社の存在意義というか、本質的な部分に興味の対象が移っています。要は、「信託こそサステナビリティ活動の本丸」ではないかと思うわけです。信託の根源的な役割は、委託者のお客さまからお預かりした大切な資産を、プロフェッショナルとしてしっかり管理・運用して次世代へと渡していくことです。その意味で、今回のような寄附と信託は相性が良いと考えます。社会はますます多様化、複雑化していますが、そうした中でも次世代につなぎたいお金やモノ、ヒトの想いは必ずあります。そこで当社の出番となるわけで、自分の一挙手一投足がサステナブルな社会の一端を担っているという意識で日々の業務に取り組んでいます。
同感です!当社の強みを活かしながら、社会課題の解決につながる仕組みを今後も構築していきたいです。
そうだよね。今は奨学金にテーマを絞っていますが、本来の寄附の役割は「富の再配分」を通じて、さまざまな社会インフラ構築のキャッシュフローを補完できることにあります。将来的には、金銭に限らず、さまざまな寄附がさまざまな用途に使われるような寄附社会の実現につなげていきたいですね。