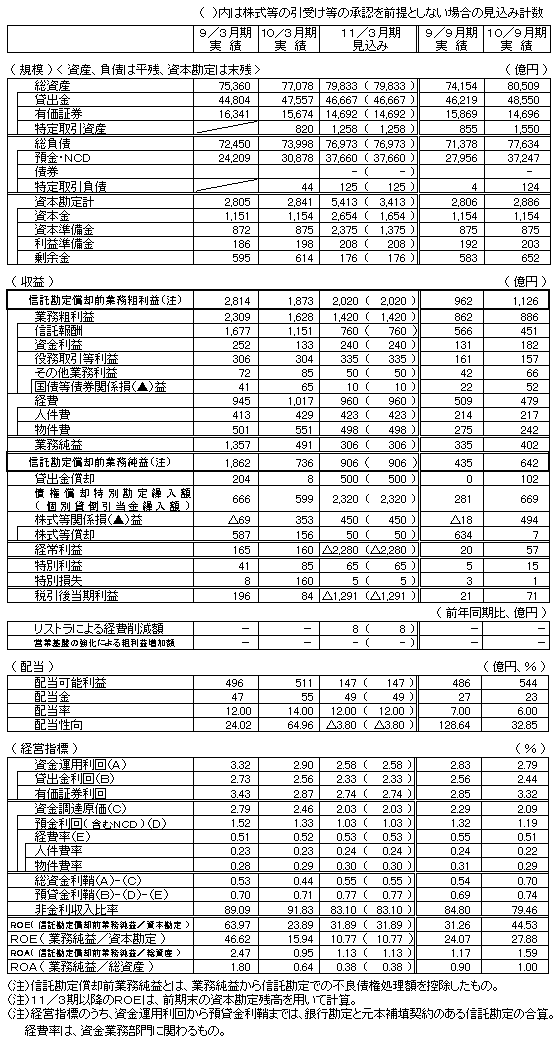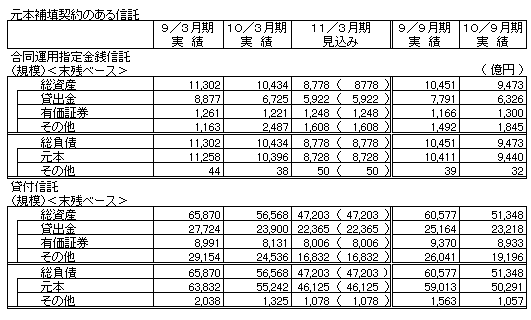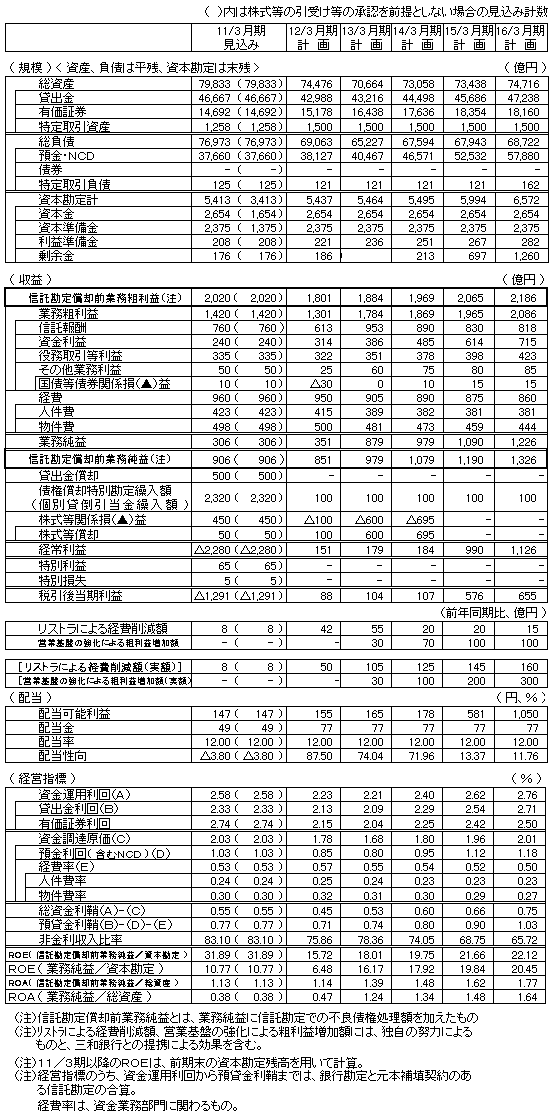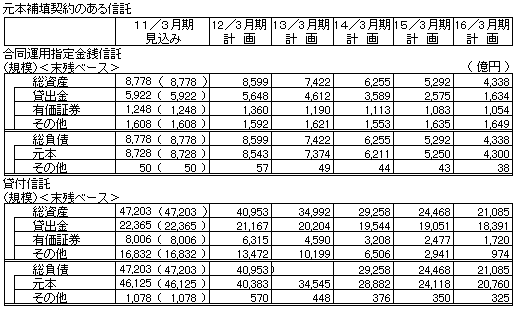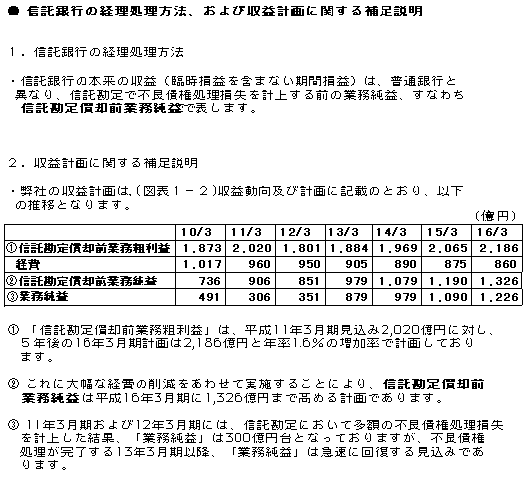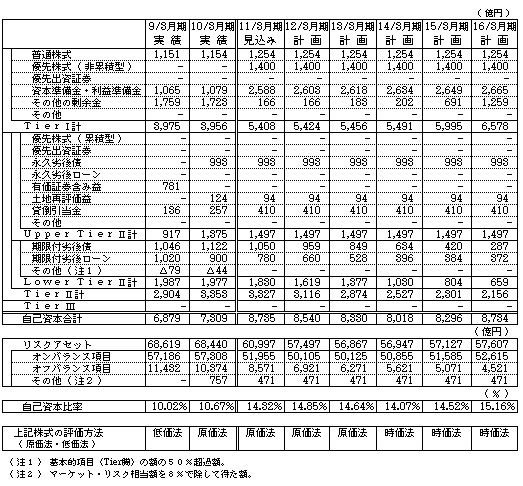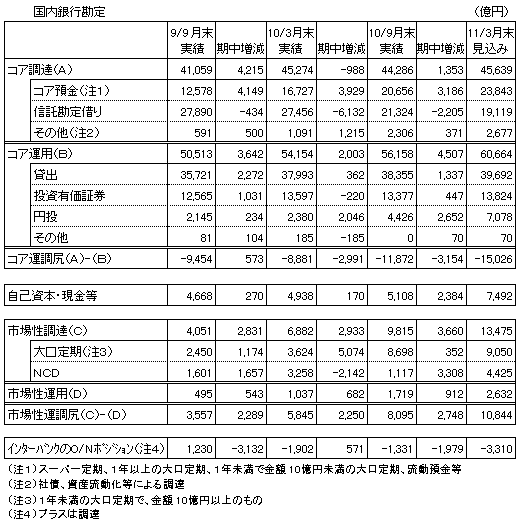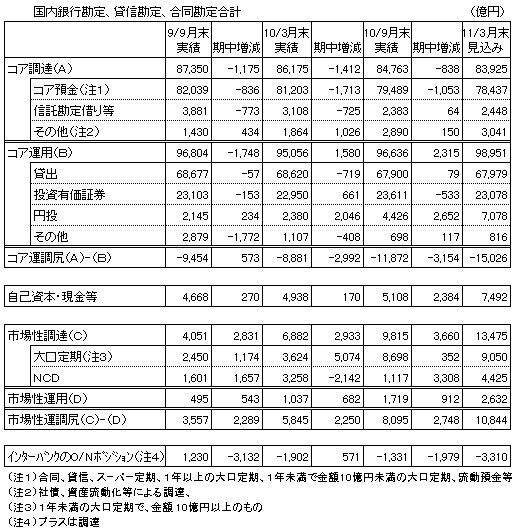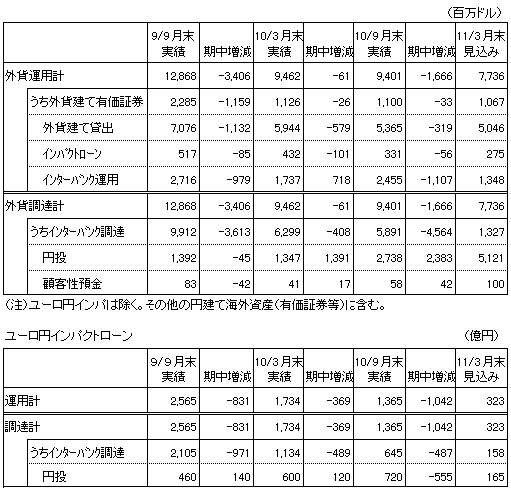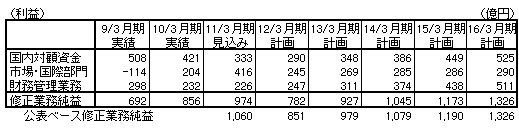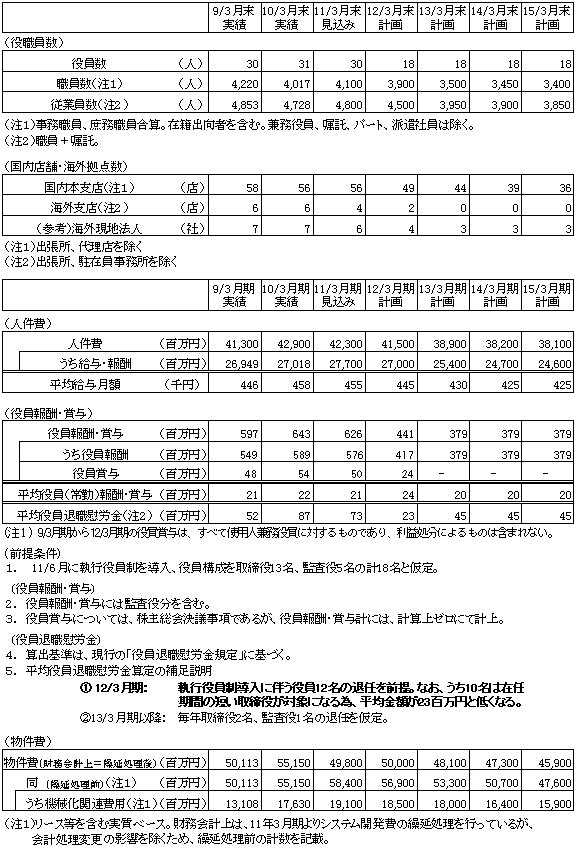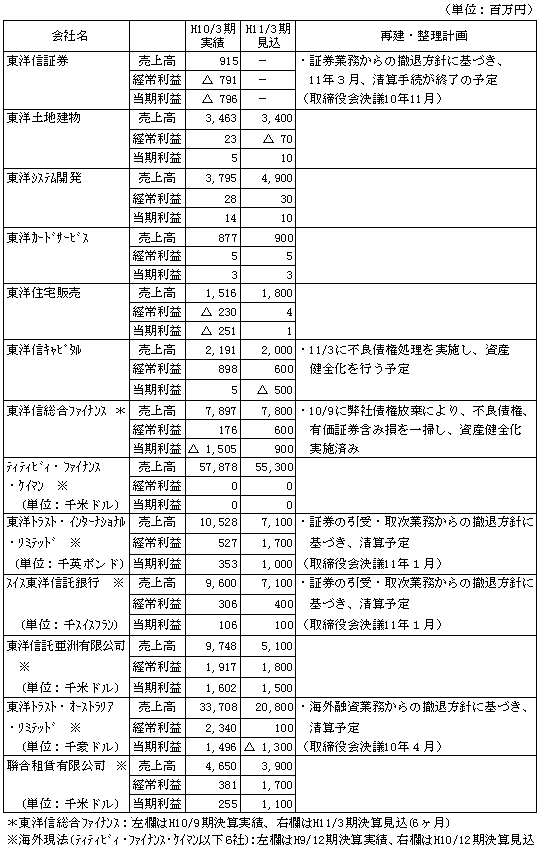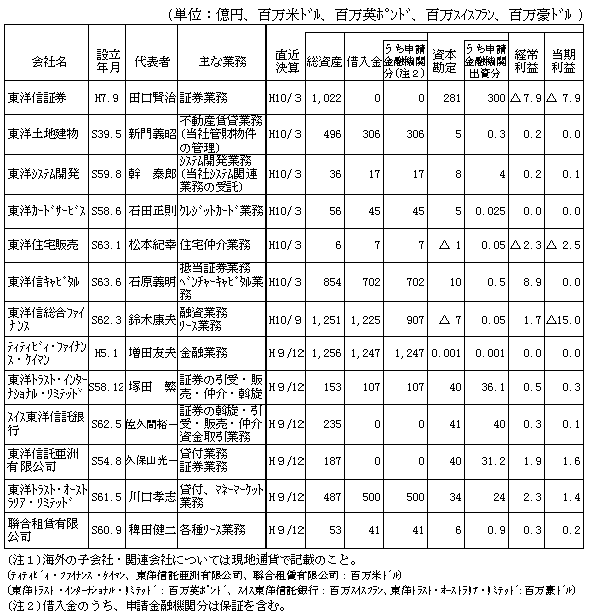2.経営の合理化のための方策
(1)経営の現状及び見通し
イ.概況
弊社は「長期経営計画2000(平成9〜11年度)」で掲げた弊社の目指すべき姿「財務管理業務に強みをもつ信託銀行」の実現に向け、戦略分野である年金、証券代行、証券運用・管理などの業務の強化に注力してまいりました。
しかし、近時、規制緩和による競争の一段の激化と、不良債権問題に端を発した金融不安の深刻化を背景に、金融機関を取り巻く経営環境は急激かつ大幅に変化しております。
信託銀行の経営課題は、
| 1) |
競争が激化する中で、競合する他の金融機関と差別化できるだけの専門性、コスト競争力を維持していくこと |
| 2) |
高度化する情報通信技術の活用や他の金融機関との提携によって、比較的少ない店舗網を補完するネットワークを構築し、顧客基盤を強化すること |
| 3) |
業務の拡大、多様化等に伴い増大する種々のリスクに耐えるために、十分な自己資本を確保すること 等 |
である、と考えております。
このような中で、弊社に対するお客さまおよび市場の信認をより確かなものとするためには、不良債権を早期かつ徹底的に処理し、これにより減少した自己資本を回復したうえで、業務の再構築を行い、戦略分野の強化の早期実現を図る必要があります。
以上のような認識に立ち、平成10年9月に経営効率化委員会を設置し、同年11月に平成12年度までの約2年半を視野に「経営効率化計画」を策定するなど、一段の経営の合理化、経営体質の強化に取り組んでおります。
また、平成11年1月には、弊社のネットワークを補完し、顧客基盤を拡充するとともに、システム投資等のコストを分担することを主眼に、三和銀行との間で、様々な業務分野において具体的な提携を検討することで合意いたしました。さらに、今般、同行に対し優先株式を中心に1,000億円の第三者割当増資を行うことを決定いたしました。
これらを通じて、図表1の通り、信託勘定償却前の業務純益を平成10年度見込みの906億円から平成15年度に1,326億円まで増強いたします。これにより、ROE(業務純益/資本勘定)を平成10年度見込みの10.8%から平成15年度に20.5%程度まで高めるなど、厳しい経営環境の中で勝ち残ることができる水準まで、収益性を向上させてまいります。
弊社の経営体質を強化し、金融仲介機能を十分に果たしていくことが、わが国金融システムに対する内外の信頼を回復する基礎になるものと認識しております。
( 図表1−1 ) 収益動向及び計画
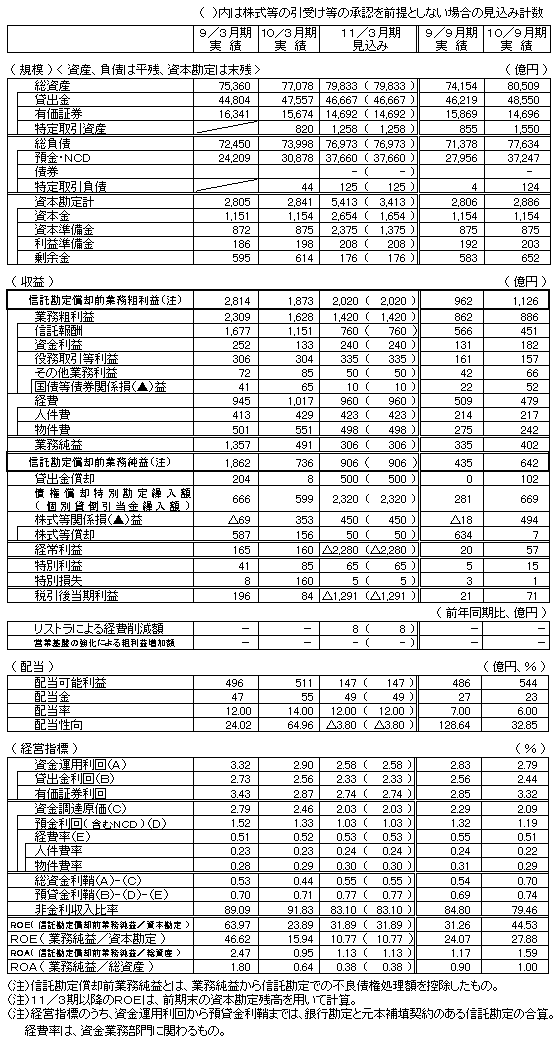
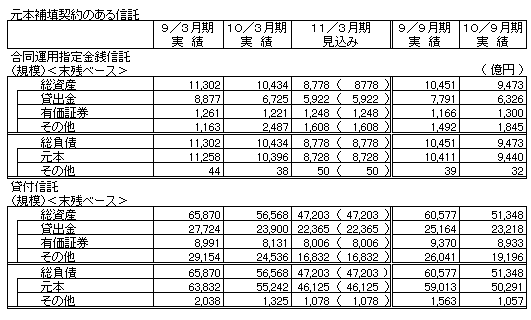
( 図表1−2 ) 収益動向及び計画
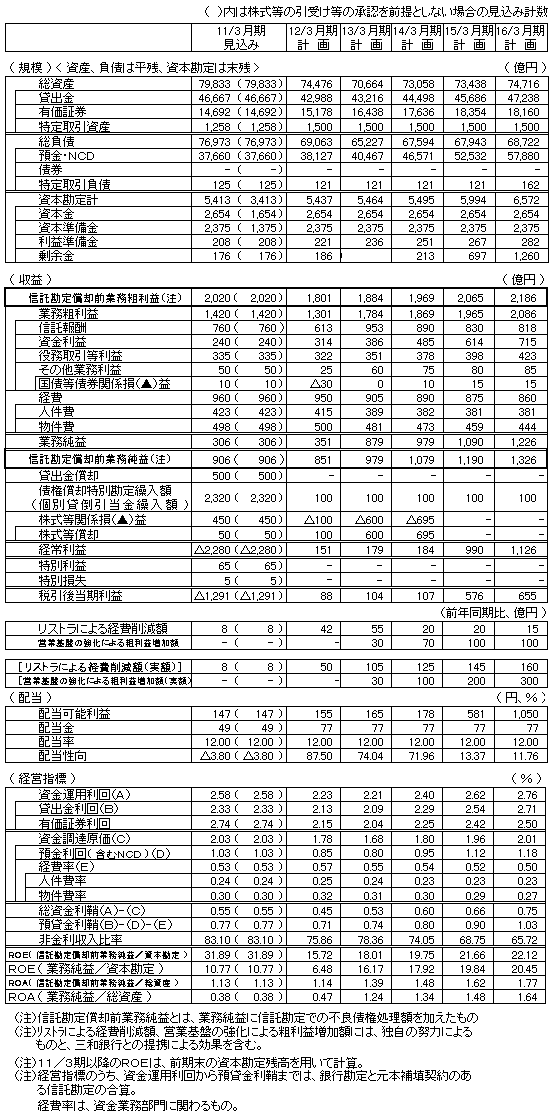
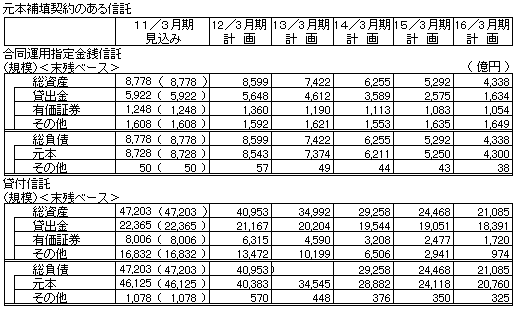
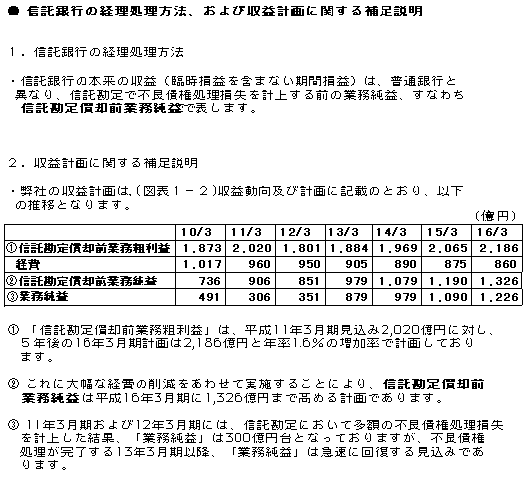
( 図表2 ) 自己資本比率の推移 ( 国際統一基準 )
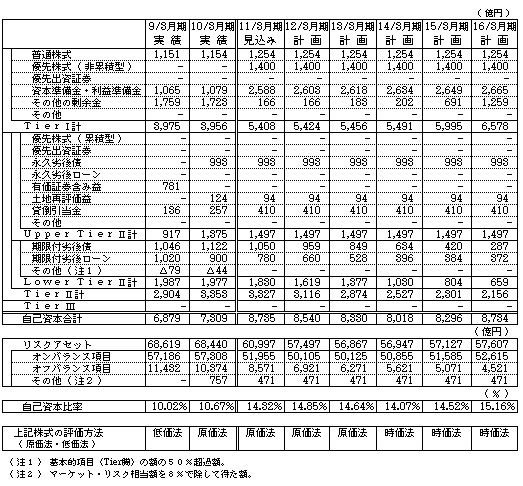
ロ.内外市場における資金運用調達の状況
(図表3)資金繰り状況
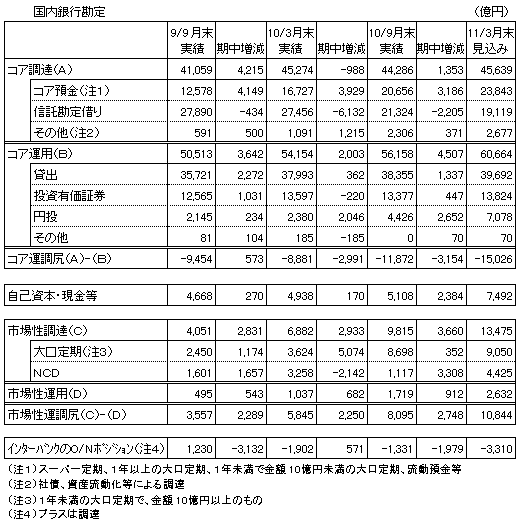
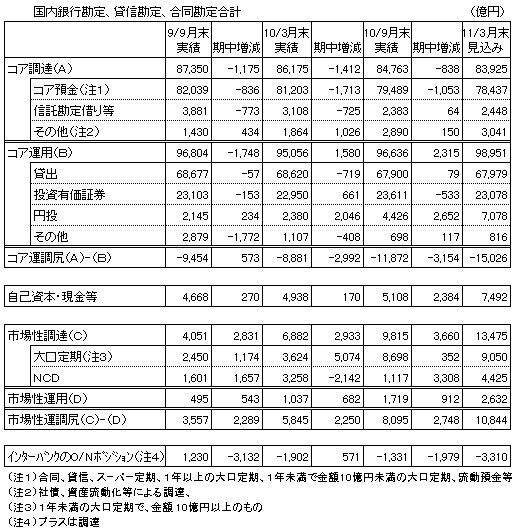
(図表4)外貨資金運用調達状況
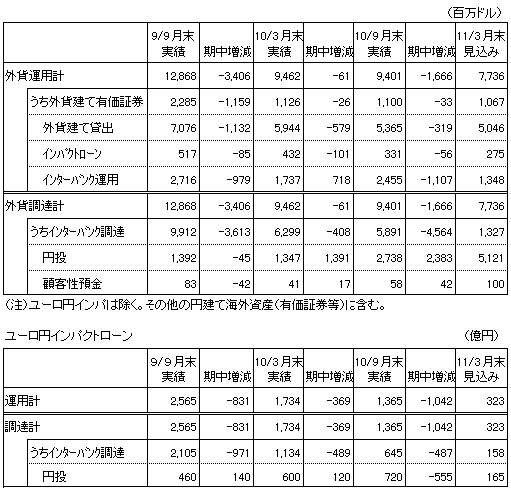
(2)業務再構築のための方策
イ.今後の経営戦略
弊社は、近時の急激かつ大幅な経営環境の変化を踏まえ、(1)イ.に記載した経営課題に対応するため、平成10年11月に「経営効率化計画」を策定いたしました。この計画は、弊社が得意とする業務に経営資源を重点的に投入し、サービスの質およびコスト面での競争力を一段と高め、専業信託銀行として確固たる地位を築くことを目指すものであります。
平成11年1月には、三和銀行との間で、様々な業務分野において具体的な提携を検討していくことで合意いたしました。さらに、同行とのグループ戦略を一層明確に打ち出し、業務提携の実効性を高めるために、同行に対し優先株式を中心に1,000億円の第三者割当増資を行うことを決定いたしました。
今後、弊社が競争力を有する各種の信託業務・財務管理機能と、同行が有する法人ミドルマーケットや個人マーケットにおける強固な業務基盤を相互に活用することを目指してまいります。
これらに加え、引き続き、資本の自力調達に努め、財務基盤をより強化してまいります。
弊社の業務再構築についての基本的考え方は、以下のとおりであります。
| 1) |
業務分野毎の収益率の分析等を通じて、一段の強化を図る分野(年金、証券代行、証券運用・管理業務を中心とする財務管理業務)と、縮小・撤退する分野(海外業務および証券引受・販売業務)を明確に区分し、経営資源の集中を進め、弊社全体としての収益力を高めること |
| 2) |
他社との戦略的提携や積極的な情報化投資により、国内店舗網や縮小・撤退する分野の機能を補完し、顧客基盤の強化を図ること |
| 3) |
種々のリスクに対応できるだけの自己資本を確保するため、資本増強および利益の内部留保等に努めること |
| 4) |
意思決定を迅速化し、業務分野毎の専門性を一層発揮するため、執行役員制と事業部制の導入を通じて、経営体制を再構築すること |
| 5) |
お客さまのニーズに対応するとともに、経営の効率化を図るため、国内店舗の再編成を実施すること |
| 6) |
権限と責任の大きい幹部職員に対して役割期待と業績成果を重視した評価・処遇体系を導入する等、透明度・納得性を一段と高めることにより職務遂行意欲の向上に繋がり、かつ外部労働市場等の変化にも適切に対応できる人事制度を確立すること |
| 7) |
業務再構築の内容を含め、積極的な経営情報の開示により、弊社の経営に対する、お客さまや市場からの信認を向上させること |
業務再構築の具体的内容は、以下のとおりであります。
| 項目 |
具体的内容 |
1. 業務のフォーカス
(1)証券戦略の見直し |
|
| 1) |
証券運用・管理業務の強化・拡充 |
| ・ |
東洋信アセットマネジメント(株)について増資・人員増強を行い、投信委託業務に参入。 |
| ・ |
日米欧3極での外国証券運用体制(米国提携先:ウェリントン・マネジメント社、英国提携先:ベイリー・ギフォード社)の拡充等、海外運用機関との提携により証券運用力を向上。 |
| ・ |
高水準のシステム投資を継続し、業界トップの証券管理業務の競争力を一層強化。 |
| ・ |
海外カストディ業務の顧客サービス力向上の観点から、米チェース・マンハッタン銀行との業務提携を検討。 |
| ・ |
三和信託銀行の統合等により営業基盤を拡大。 |
| 2) |
証券子会社の清算 |
| ・ |
東洋信証券(株)およびロンドン・スイスの証券現法(TTI、TTS)を整理、公共債ディーリング業務は銀行本体に一本化。 |
|
(2) 海外の銀行業務か
らの全面的撤退 |
| 1) |
平成12年度中を目処に、海外の銀行業務から全面的に撤退 |
| 2) |
海外拠点の廃止 |
| ・ |
12拠点(6支店、2駐在員事務所、4現地法人)を廃止。 |
| ・ |
海外の銀行業務から全面的に撤退するのに伴い、現在の19拠点を、証券運用・管理業務を中心とする9拠点に再編・統合。 |
| 3) |
海外部門人員の大幅削減 |
| 4) |
海外部門経費の圧縮 |
| ・ |
年間経費を45億円程度圧縮。 |
| 5) |
三和銀行との業務提携による機能補完 |
| ・ |
海外業務の再編にあたっては、三和銀行との業務提携により、機能を補完。 |
|
(3) 確定拠出型年金分
野への参入 |
| 1) |
確定拠出型年金に関する営業推進を行なう「セールス・プランニング会社」を三和銀行と共同で設立。 |
| 2) |
日本ティー・ピー・ピー株式会社への事業参画および出資。 |
| 3) |
投信商品、信託商品など運用商品メニューのパッケージ化の協働 |
|
(4) 法人営業基盤の強
化 |
| 1) |
法人ミドルマーケット(中堅・中小企業)における三和銀行との協働体制を構築し、営業基盤を拡大。 |
| ・ |
企業年金に関するニーズ把握と市場開拓の協働 |
| ・ |
株式公開を目指す企業への相互補完体制の構築 |
| ・ |
企業の不動産ニーズへの対応策を一元化 |
| ・ |
不動産証券化業務の共同展開 |
|
(5) 個人財務相談業務
の強化 |
| 1) |
個人営業特化店舗のミッションを明確化のうえ、財務アドバイザーを大幅増員(現状40人→100人)。 |
| 2) |
資産家層取引における三和銀行との協働体制を構築 |
|
| |
2. 国内店舗網の再編
(1) 概要 |
|
| 1) |
現有フルライン型店舗から、法人営業機能を分離のうえ集約、分離後の店舗を個人営業に特化する店舗に転換。店別ミッションの明確化により、顧客サービスの高度化、店舗、人員の適正化等の業務効率化を推進。 |
| 2) |
上記1) の再編、店別採算の見直し等を踏まえて、国内店舗の約3割に相当する15〜20カ店について出張所化ないし統廃合を検討。 |
| 3) |
三和銀行とのATMの共用化、多機能店舗の共同展開などにより、店舗網を補完。 |
|
(2) 具体的施策
(東京・大阪地区) |
| 1) |
東京・大阪地区にある店舗の法人営業機能を分離し、6カ所に集約、分離後の店舗は個人営業に特化。 |
| 2) |
東京・大阪地区では、計画期間中に、新たに10カ所程度の個人営業特化型のミニ店舗(インストアブランチ等)・出張所の開設、土日の営業の実施、営業時間の延長、遺言・相続・不動産・ローン・資産運用等に関する土日相談会の開催、インターネットバンキング等の非対面チャネルの拡充等のサービス開始も検討。 |
|
(3) 具体的施策
(東京・大阪以外) |
| 1) |
東京・大阪地区以外の地域についても総合店舗と個人中心店舗のミッションを明確化。10程度のエリアにブロック制を拡大、母店の営業支援により、構成店・出張所の営業体制を効率化、顧客サービスを向上。 |
|
| |
3. 業務の効率性向上
(1) 間接部門の効率化
等 |
|
| 1) |
システム開発、システム運営、管財業務、営業店後方事務の4部門を子会社・関連会社に移管し、効率性、機動性、専門性を向上。 |
| 2) |
三和銀行との各種システムの共同開発により、コストを削減。 |
|
(2) 積極的な情報化投
資 |
| 注力分野である財務管理業務を中心に、情報通信技術の発達を最大限に活用して、業務の効率化、サービスの高度化を推進。 |
| |
| |
具体的な情報化投資 |
| ・ |
証券管理業務:約定データ自動取込、約定管理システム |
| ・ |
証券代行業務:入力事務のイメージ処理、株主異動報告の電子化 |
| ・ |
年金業務:受給者管理のオンライン化、退職給付計算業務システム |
| ・ |
不動産業務:全店ベースの不動産地図情報システム |
| ・ |
資金業務と財務管理業務を統合した個人CIF(顧客情報ファイル)の構築 |
| ・ |
インバウンドのテレフォンバンキングシステムの導入 |
|
| (3)従業員数の削減 |
| 1) |
平成10年9月末現在約4,900人の従業員を、新規採用の抑制等により、約1,100人(2割相当)削減。 |
|
| (4)人件費の削減 |
| 1) |
従業員については賞与を15〜20%削減。 |
| 2) |
課長級以上について給与の一部カットを検討。 |
| 3) |
社宅制度の見直し、従業員預金の撤廃等、福利厚生制度や、家族手当等の諸手当についても大幅に見直し。 |
| 4) |
地域採用の拡大により店舗運営コストを圧縮。 |
|
| |
4. 執行役員制、事業部
制の導入
(1)執行役員制の導入 |
| |
| |
| 平成11年6月より執行役員制を導入し、経営の意思決定・監督機能と執行機能を分離、コーポレート・ガバナンスを強化。 |
| 1) |
取締役数を10〜15名に削減、取締役会を少数の取締役によって構成し、「戦略決定機関」・「業務執行の監督機関」としての役割を一層強化。 |
| 2) |
執行役員に業務執行権限を委譲し、「戦略の実行」を徹底。 |
|
| (2) 事業部制の導入 |
執行役員制の導入にあわせて事業部制を導入し、各執行役員の責任と権限を一層明確化、各業務における専門性を向上。
|
| |
5.人材の養成等
(1)人材の養成 |
| |
| 1) |
高度な専門性を有する人材を多数育成するため、各種資格の取得を奨励、支援。 |
| (平成10年9月末の各種資格取得者数) |
| 年金アクチュアリー |
16名 |
| 証券アナリスト |
224名 |
| 不動産鑑定士・同士補 |
140名 |
| 中小企業診断士 |
25名 |
| 情報処理技術者1種 |
47名 |
|
| 2) |
平成8年11月には「専門職制度」を導入し、特定分野のプロフェッショナルを志向する人材の処遇を明確化。この制度に基づき、平成10年9月末現在161名を専門職として処遇し、専門職位に応じた職務手当を支給。 |
| (平成10年9月末の各種資格取得者数) |
| 業務管理(法務、情報) |
18名 |
| 調査 |
2名 |
| 個人営業 |
18名 |
| 資金・証券 |
55名 |
| 証券代行 |
8名 |
| 年金 |
24名 |
| 不動産 |
36名 |
| (合計 |
161名) |
|
|
(2) 採用、給与体系の改
定 |
| 1) |
労働市場における流動性が高まるなか、中途採用を積極化し、人材の確保、充実策を多様化。特に、戦略分野では、高度な専門知識・ノウハウを有する人材を採用、戦力を拡充。 |
| 2) |
平成8年11月の人事制度の改定により、職務責任や業務貢献度を処遇に十分反映させるため「職務給」を導入。一定資格以上の職員について、本俸、家族手当及び定期昇給を廃止。また、総合職及び地域総合職の定期昇給は49才で停止。 |
|
(3) 組織の活性化、モラ
ールの向上 |
| 1) |
部室店長等、管理職層へ年俸制を導入。 |
| 2) |
営業店長、出張所長の社内公募制を導入。 |
| 3) |
一般職の地域総合職への転換促進。 |
|
他社との戦略的提携について
弊社は、平成11年1月、三和銀行との間で、日本版ビッグバンに対応し、グローバルな金融市場での競争力を確保すべく、様々な業務分野において具体的な提携を検討していくことで合意いたしました。
さらに、同行とのグループ戦略を一層明確に打ち出し、業務提携の実効性を高めるために、同行に対し優先株式を中心に1,000億円の第三者割当増資を行うことを決定いたしました。
これらは、弊社が市場競争力を有する各種の信託業務・財務管理機能と、三和銀行が有する法人ミドルマーケットや個人マーケットにおける強固な業務基盤を相互に活用することにより、業務面での協力関係の構築を目指すものであります。
両社が高度化・多様化するお客さまのニーズに対応した、付加価値の高く、かつ競争力のある金融サービスの提供を実現することで、中長期的には顧客基盤の飛躍的な増強と収益体質のさらなる強化に繋がるものと認識しております。
また、英ベイリー・ギフォード社および米ウェリントン・マネジメント社との間の合弁会社設立等により外国証券運用業務における日欧米の3極体制を確立し、運用力の向上を図っているほか、弊社の設立母体の一つである野村證券や、親密な関係にある国際証券とも、証券代行業務等における情報連携関係に加えて、以下のような分野を中心に協調・提携関係を一層強固なものにしていく方針であります。
| ・ |
野村證券 |
確定拠出型年金制度におけるレコード・キーピング事業への参画を検討 |
| ・ |
国際証券 |
資産流動化業務の共同推進、資産家層取引におけるノウハウの相互提供 |
《三和銀行との業務提携の中で検討していく項目》
1.確定拠出型年金分野における共同事業化
2.業務インフラ(システム・ATMなど)の共用化
3.海外業務など重複する業務・機能の統合
4.法人ミドルマーケット取引における協働体制の構築
5.資産家層取引における協働体制の構築 |
( 具体的に検討する提携内容 )
| 1. |
確定拠出型年金分野における共同事業化について |
|
○ |
両社は、確定拠出型年金分野における全面的な提携に向け、両社に専任担当者を置き、以下の項目について検討・具体化を進める。 |
| |
1) |
確定拠出型年金に関する営業推進を行なう「セールス・プランニング会社」の共同設立 |
| |
2) |
日本ティー・ピー・ピー株式会社※への当社の事業参画および出資
| ※ |
コールセンター機能を活用した投資情報提供サービスや事務受託を行なうことを目的とした、パートナーズ投信株式会社と三和銀行の共同出資会社
(現在の出資比率は、パートナーズ投信:三和=95:5) |
|
| |
3) |
投信商品、信託商品など運用商品メニューのパッケージ化に関する協働検討
|
| |
4) |
その他、事業展開に必要なインフラ関連業務につき、他社との連携を含め具体化
|
| 2. |
業務インフラの共用化に関する検討 |
|
○ |
両社は、事務・システム等における投資効率を向上させるため、業務インフラに関する共同開発・共用化の検討に取り組む。 |
|
|
1) |
システムについての共同開発テーマの選定と共同研究 |
|
|
2) |
手形交換・メール搬送などの相互委託 |
|
|
3) |
ATMの共用化 |
|
|
4) |
多機能店舗の共同展開 など |
| 3. |
重複する業務・機能の統合 |
|
○ |
両社は、以下の業務・機能について、各々移管・統合することにより、事業競争力の一層の強化と効率化を図ることを検討する。 |
|
|
1) |
三和銀行は、弊社の海外貸出業務からの撤退に全面的に協力 |
|
|
2) |
当社は、三和信託銀行を統合 |
|
|
3) |
当社は、三和銀行の内外カストディー業務を統合 など |
| 4. |
法人ミドルマーケット取引における協働体制の構築 |
|
○ |
両社は、法人ミドルマーケットにおいて、高度な金融サービスを提供し、事業基盤の拡大を図るため、取引推進に関する協働体制の構築を検討する。 |
|
|
1) |
企業年金に関するニーズ把握と市場開拓の協働 |
|
|
2) |
株式公開を目指す企業への相互補完体制の構築 |
|
|
3) |
弊社の不動産業務を軸に企業の不動産ニーズへの対応を一元化 |
|
|
4) |
不動産証券化業務に関する共同研究 など |
| 5. |
資産家層取引における協働体制の構築 |
|
○ |
両社は、個人資産家層向けに付加価値の高い金融サービスを提供するため、協働体制の構築を検討する。 |
|
|
1) |
グループ機能を相互活用した総合財務相談・資産管理業務への取組み |
|
|
2) |
個人不動産ニーズの当社への集約化 など |
|
《三和銀行との業務提携の効果》
三和銀行との提携が、収益面に直接的に与える効果としては、平成16年3月期にかけて、財務管理業務を中心に年間60億円程度発生するものと見積り、収益計画に織り込んでおります。加えて、海外貸出業務からの撤退手続が促進されることにより、平成13年3月期にかけて、累計10億円程度の収益効果を見込んでおります。
さらに、システムの共同開発により、以下の投資負担軽減を見込んでおります。
| ・ 確定拠出型年金事業に関わるシステム開発 |
100〜150億円 |
| ・ 次世代営業店システム、リスク管理システム等 |
30〜 50億円 |
また、中長期的には、年金業務や証券代行業務等の財務管理業務において、顧客基盤が一段と強化されることが見込まれます。
ロ.主要部門別の純収益(部門毎の経費を勘案)動向
(図表5)部門別純収益動向
(社内管理会計ベース)
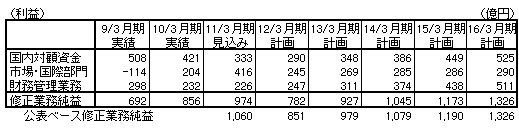
(1)基本的な考え方
・本表は、社内管理会計ベースとなっております。
・利益は、公表ベースの修正業務純益(信託勘定の不良債権処理を行う前、かつ、一般貸倒引当金繰入前)に一致いたします(9/3月期は、政令改正に伴う貸付信託勘定の特別留保金取崩益を除く。)
・弊社では、平成10年度中間決算より、ソフトウエア開発費用につきましては、従来の、支出時に費用認識する方法から、税法の定める方法により5年間で均等償却する方法へ変更しておりますが、本表では、比較可能性の観点から、従来の支出時費用認識の方法に戻して示しております。
(2)収益
・平成9年度の修正業務粗利益1,873億円は、平成10年度には、有価証券運用を中心とする市場部門の好調により2,020億円まで上昇する見込みです。
・平成11年度は、金利変動による影響を一時的に受け、貸出業務を中心とする国内対顧資金部門、及び、市場部門収益の減少により、修正業務粗利益は1,801億円となる見込みです。
・平成12年度以降、財務管理業務収益を中心に、三和銀行との提携による効果も現れ、順調な収益拡大を見込んでおり、平成15年度には修正業務粗利益2,186億円を計画しております。
(3)経費
・弊社は、平成9年度からスタートした長期経営計画「長計2000」におきまして、他社との差別化を推し進めるべく、戦略的システム投資を行っており、経費は平成10年度1,046億円となります。
・平成11年度以降、業務再構築による効果も現われ、平成15年度には860億円を計画しております。
(4)利益(本表)
・修正業務純益は、平成10年度974億円から、平成11年度782億円に一時的に減少するものの、その後順調に増加し、平成15年度には1,326億円となる見込みです。
(5)経費率
・経費率は、平成10年度51.8%から、12年度以降、収益増加、並びに経費削減効果により、平成15年度には39.3%まで低下するものと考えております。
ハ.リストラ計画
業務のフォーカス、国内店舗網の再編、業務の効率性向上等の業務再構築に基づき、以下のリストラを実施し、従業員1人当たりの効率性を更に高めてまいります。
リストラ計画の概要
|
10年3月末
(平成9年度) |
16年3月末
(平成15年度) |
増減
(同率) |
ピーク比
(同率) |
| 役員数(人) |
31 |
18 |
-13(-42%) |
5年3月末比
-15(-45%) |
| 従業員数(人) |
4,728 |
3,850 |
-878(-19%) |
5年3月末比
-1,734(-31%) |
| 内外店舗数(店) |
62 |
36 |
-26(-42%) |
6年3月末比
-33(-48%) |
| 役員報酬・賞与(億円) |
6.4 |
3.8 |
-2.6(-41%) |
2年度比
-6.5(-63%) |
| 人件費(億円) |
429 |
381 |
-48(-12%) |
4年度比
-71(-16%) |
| 物件費(億円) |
551 |
444 |
-107(-19%) |
3年度比
-142(-24%) |
| 経費合計(億円) |
1,017 |
860 |
-157(-15%) |
3年度比
-219(-20%) |
1人当たり効率性(百万円)
(信託勘定償却前業務純益
/従業員数) |
15.6 |
34.4 |
+18.9(+121%) |
− |
| 1) |
人件費 |
| 以下の施策を実施し、人件費を平成9年度比48億円削減する計画であります。 |
| ・ |
新規採用の抑制等により従業員を削減。 |
| ・ |
従業員については賞与を15〜20%削減。 |
| ・ |
課長級以上について給与の一部カットを検討。 |
| ・ |
社宅制度の見直し、従業員預金の撤廃等、福利厚生制度、家族手当等の諸手当についても大幅に見直し。 |
| ・ |
地域採用の拡大により店舗運営コストを圧縮。 |
| 2) |
物件費 |
| 一般物件費を抜本的に見直すとともに、重点分野以外のシステム投資を絞り込む等、物件費を平成9年度比107億円削減する計画であります。 |
| 3) |
役員・相談役および顧問 |
| ・ |
執行役員制の導入に伴い、役員数を平成9年度比13名削減する計画であります。 |
| ・ |
相談役(2名)につきましては、平成11年2月末付けで全員退任いたしました。なお、相談役制度は定款において定められているため、平成11年6月の定時株主総会において定款を変更のうえ、廃止する予定です。 |
| ・ |
平成11年3月1日現在、顧問契約を締結している弊社役員経験者等は13名となっておりますが、各々の契約期間(全員1年契約)満了後は契約更新は行わない方針であり、1年以内に全員契約終了といたします。 |
| 4) |
遊休不動産 |
今後使用する予定のない役職員の社宅および寮については、全て処分する基本方針のもと、8物件(時価15億円相当)の売却手続きに着手しております。また、上記1) の社宅制度見直しに伴い、今後必要性が低下する社宅および寮も処分していく方針です。
なお、弊社は、創業以来、ゲストハウスやグランド等は保有しておりません。 |
(図表6)リストラ計画
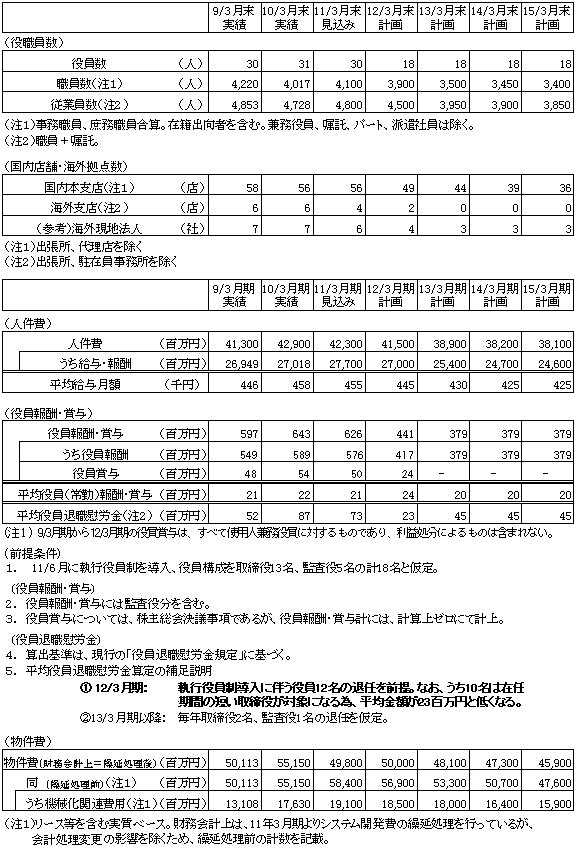
ニ. 子会社・関連会社の収益等の動向
・ 国内外における子会社・関連会社設立の目的と管理の状況
国内外における子会社・関連会社は、1) 弊社業務の一部を移管することを通じ、業務の効率化等に資すること、また、2) 国内外における金融関連業務の展開等を通じ、幅広くお客様のニーズにおこたえすること、を主たる目的として設立しております。
弊社の子会社・関連会社は、以下のように、厳正に管理しております。
| 1) |
子会社・関連会社の経営方針等の重要事項の決定については、弊社の関連会社委員会等での審議のうえ、行われております。 |
| 2) |
子会社・関連会社の業務執行状況について、月次あるいは定期的に弊社の経営陣に報告を行っております。 |
| 3) |
子会社・関連会社の業務運営状況をチェックするため、弊社は定期的に業務調査(銀行による監査等)を実施しております。 |
また、改正銀行法施行に伴う、弊社のグループ範囲見直しへの対応強化のため、平成10年10月に、関連事業部を新設致しました。同部では、子会社・関連会社の経営管理、経営方針の決定、経営計画等に関する助言・指導を行い、管理体制を強化しております。
・ 子会社・関連会社の収益等の動向
子会社・関連会社の収益等の動向および再建・整理計画は、下表の通りであります。
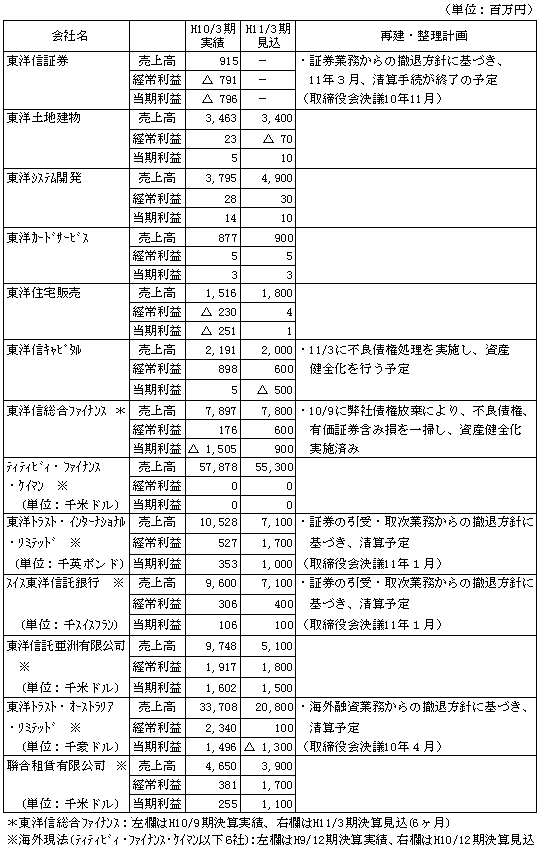
(図表7)子会社・関連会社一覧(注1)
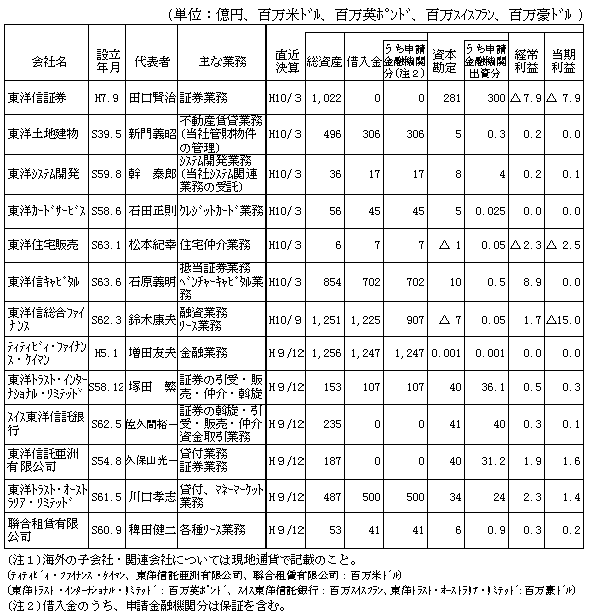
| (注) |
1) 銀行法等における子会社、2) 「事務ガイドライン1-6」に規定している関連会社(上場会社も含む)を記載しております。但し、原則として弊社の与信額が1億円以下の場合は、記載しておりません。
なお、海外現法のうち、弊社からの借入金がなくとも、弊社からの預かり金を有する会社については記載しております。 |