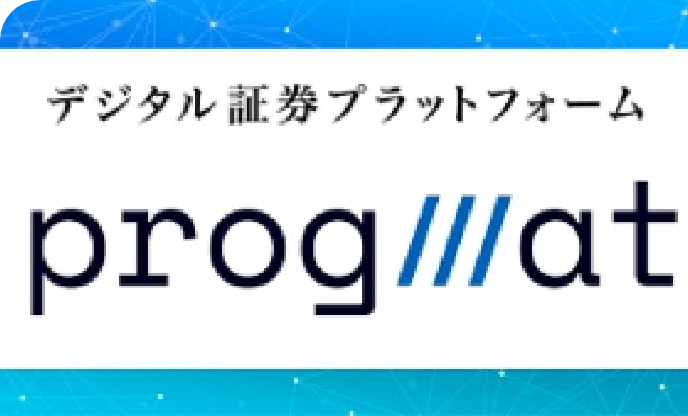“Progmat”
「ブロックチェーン技術で、可能になる世界」
ブロックチェーン技術を使った「Progmat」は、セキュリティ(有価証券)をブロックチェーン上で発行する「セキュリティトークン(デジタル証券)」の発行・管理プラットフォームで、その特徴は、取引にかかる中間コストが自動化によって省けるので、投資商品の小口化が可能になるということです。投資の口数をどんなに分割してもコストはほぼ変わらないので、これまでコストの問題で小口化されなかった、大口でのみ購入可能な、プロのみを対象にしていたような投資商品についても、小口化して多数の個人投資家に販売できるようになります。
私は、お客さまの経営戦略・課題を踏まえた不動産の活用方法やCRE(企業不動産)戦略に関するコンサルティングを担当しているのですが、いくつか早速、「Progmat」を活用したアイデアを考えて、提案してみました。
どんな提案か、ご紹介いただけますか。
たとえば、単純な資金調達の目的だけではなく、沿線ファンを増やしていくことにフォーカスしたアイデア。住民を巻き込んで、将来的な開発をするための投資を募るだけではなく、沿線ならではのポイントが付与されるポイントプログラムと、このProgmatをつなげられないかなど、さまざまな可能性を議論しています。
それは面白いアイデアですね。たとえば、沿線の住民が、駅前開発の資金をセキュリティトークン=デジタル証券の形で購入して、その開発がうまくいくと、そのトークンの価値自体も上がって、住民もトクするという仕組みですね。
そうですね。こういう仕組みがあることで、沿線の住民が、自ら沿線の活性化に取り組むきっかけが生まれると思います。
これをアナログでやろうとすると、相当大変です。まず沿線住民1万人が参加するとなると、権利書をつくったりするのも膨大な事務作業が必要になるわけです。ところが、Progmatの場合、紙にサインするとか、権利書を送付するとか、一切なく全てデジタルで完結します。
もうひとつ、従来の株や債券と、セキュリティトークンの違いは、誰が持ち主=権利者なのかがリアルタイムでわかるという点ですよね。
そうですね。これまでは、例えば株式の場合、株主名簿ができるまで一定期間かかるので、リアルタイムで誰が株主かよくわかりません。その一方で、Progmatは、誰が投資家かを記した名簿、「原簿」っていうんですけれども、それを管理して、売買があっても、リアルタイムで誰が株主かを反映していくので、誰が権利者なのかをすぐに確認できます。
そういったデータを使うことで、投資家の方に付帯権利として、ギフトや割引券をお渡しすることによって、地域の活性化につなげたりと可能性は広がりますね。
「誰でも、超優良物件のオーナーになれる」

じつは「Progmat」の1号案件は、渋谷の高級レジデンスの案件です。J-REIT(日本版不動産投資信託)なんかだと中身にいろいろな不動産が入っていて、組み入れられている物件が入れ替わったりするので、自分がどの不動産のオーナーだという意識を持ちづらいと思いますが、今回の案件は、ひとつの物件なので、自分の物件として愛着が持てることもポイントのひとつです。
J-REITのように、複数の物件を入れることも可能なんですよね。
もちろん、それも可能です。J-REITは上場商品ですが、「Progmat」で扱うデジタル証券は非上場というのも大きな違いです。上場していると売買がしやすいというメリットがある一方、金融危機があるとパニック売りなんかがあって、その不動産の実際の価値に関係なく価格が暴落したりします。非上場だとそうした影響を受けにくいというメリットがあります。
手軽に投資できるということも重要ですよね。
スマホから証券会社のサイトにアクセスしたり、アプリを起動して、そこに並んでいるデジタル証券の銘柄を見ていただき、購入することができます。その不動産の価値が上がると、セキュリティトークンの価値も上がったり、賃料などをベースとした配当も出ます。
もちろん配当や利回りも重要ですが、「Progmat」の場合は、短期的な損得だけじゃなく、そのエリアにもともと住んでいたとか、この不動産開発プロジェクトを応援したいという想いのある方も集まってくれるんじゃないか、と思っています。
そのプロジェクトを応援したくなるという意味では、今後の案件として、プロスポーツチームなんかも面白いですね。チームの運営費や球場の改修費などの資金調達に「Progmat」の仕組みを使うことで、ファンがチーム運営を支えて、チームはそのお礼にチケットやグッズを送るとか。
不動産プロジェクトの話に戻りますが、いま私が提案している案件で、「スマートシティ構想」があります。スマートシティとは、まちの様々な機能が通信技術でつながっていて、サステナブルなまちのことです。こうしたまちの開発にもセキュリティトークンを活用することができると思っています。この場合は、1つの建物や物件というよりもまち全体の歩道を整備するために使うとか、スマートシティ内でのイベント開催費用を調達するとか、いろいろな可能性が広がりますね。
「Progmatが創り出す未来」

Progmatが目指すところは、一つのプラットフォームで、社債とか証券化商品、不動産とか、さまざまな金融商品を取り扱って、いつでもどこでも365日24時間、小口の投資家がさまざまな運用機会にアクセスできて、一方で資金を必要とする人たちは資金調達が可能となる世界です。
最初の案件は、不動産案件が中心となると思いますが、Progmatで扱うものは、不動産に限りませんよね。
そうですね。さきほどスポーツチームの話をしましたが、スポーツも含めたエンターテイメントの世界は親和性が高いと思っています。たとえば、映画を作る場合、制作委員会とか作られると思うんですけど、そういう委員会の権利を小口化して、応援したい人に買ってもらうとか。映画や小説、漫画の著作権のセキュリティトークンを買えるようになると、誰もが昔のパトロンみたいな存在になって、エンターテイナーを応援できる。大きく成功すれば、投資としても大きなリターンになるかもしれませんね。
わたしはサステナビリティという観点からも、Progmatを使ったインフラがもたらす可能性は大きいと思っていまして、投資のテーマを社会課題と照らし合わせて、わたしたちが意志を持って、投資先を選んでいくことで「安心・豊かな社会」を創り出すことができると思っています。
たとえば、地域活性化をテーマにした投資とか。あとは、燃料電池のようなインフラ投資とか、そういう分野に投資することによって、環境問題の改善、サステナビリティに貢献できますよね。
現状、信託銀行で取り扱っている不動産業務では、残念ながらデベロッパーではありませんので、開発そのものはできません。でも、Progmatを活用することによって、地域の活性化、まちづくりなどにも貢献できるという部分に、個人的にも非常に期待しています。また、我々が今までなかなか手をつけられてこなかった海外不動産や環境不動産といったようなところも、Progmatの機能を活用することによって、新たにサービス提供できれば、より幅が広がるのかなと考えているところです。
まさに新しい世界の扉が開かれたと思っているんですよ。クラウドファンディングとも似ているようで決定的に違うのは、これは有価証券なので、流動性が高くて売買できるんですね。最初は、証券会社を通じての売買になりますが、将来的には、投資家間で直接売買マッチングをすることで、コストがかからないカタチを目指しています。
Progmatの活用方法については、わたしたち自身も、現段階で何か明確な答えを持ち合わせているわけではないので、良い意味で、お客さまと一緒にコミュニケーションを取ってアイデアを出し合いながら、ひとつひとつ形にしていけることに、非常にやりがいを感じています。
この壮大なチャレンジは、まだ始まったばかりで、先駆者としての苦労もありますが、この挑戦自体がとても楽しみです。