三菱UFJ信託銀行は、MUFGグループのパーパス(存在意義)「世界が進むチカラになる」、自社のサステナビリティ活動指針『
「安心・豊かな社会」を創り出す信託銀行
』を通じて、SDGs達成に取り組むだけでなく、機関投資家としての立場から、国内外の企業さまのSDGsへの取り組みを考慮したサステナブル投資を行っています。
そのリーダーであるサステナブルインベストメント部の加藤正裕が、話題の企業のSDGs担当者とサステナブルな社会の実現を目指して語り合うスペシャル対談企画「サステナビリティ未来会議」。
9回目となる今回は、特別企画としてこの領域の研究者との鼎談を実施。
ゲストに慶應義塾大学総合政策学部教授の國領二郎氏、サステナビリティ学の研究者の笹埜健斗氏をお迎えし、これまでの企業さまとの対談から見えてきた持続的な成長を実現するための共通点や課題などを振り返りつつ、世界の最新動向も踏まえながら、研究者と投資家の視点から今後の日本企業のSDGs活動の「鍵」について提言していきます。

慶應義塾大学
総合政策部 教授
國領二郎氏
1982年東京大学経済学部卒。日本電信電話公社入社。1992年ハーバード・ビジネス・スクール経営学博士。1993年慶應義塾大学大学院経営管理研究科助教授。2000年同教授。2003年同大学環境情報学部教授、2006年同大学総合政策学部教授(現在に至る)などを経て、2009年より2013年総合政策学部長、2013年より2021年5月慶應義塾常任理事を務める。 主な著書に「オープン・アーキテクチャ戦略」(ダイヤモンド社、1999)、「ソーシャルな資本主義」(日本経済新聞社、2013年)、「サイバー文明論持ち寄り経済圏のガバナンス」(日経BP 日本経済新聞出版社、2022年)、櫻井美穂子・國領二郎共著「ソシオテクニカル経営人に優しいDXを目指して」(日経BP 日本経済新聞出版、2022年)がある。

サステナビリティ学者
SDGs 社会起業家
笹埜 健斗氏
サステナビリティ学者(慶應義塾大学 SFC 研究所所員、サステナビリティ総合研究所所長)、SDGs 社会起業家(株式会社 Scrumy 代表取締役)。高校時代に生死の境を彷徨い、哲学に目覚める。 国際哲学オリンピック出場、京都大学法学部、東京大学大学院情報学環・学際情報学府を経て、各 業界の最高サステナビリティ責任者(CSO: Chief Sustainability Officer)や SDGs 戦略顧問を歴任。 現在、SDGs(持続可能な開発目標)を経営や教育に応用するための「サステナビリティ学」の第一人者として、持続可能な社会の実現に向けた共同研究や ChatGPT を活用したプロンプトエンジニアリング等の技術開発をリードする。 主な単著論文に「持続可能な IoMT セキュリティに向けた法政策―サステイナビリティ学の視座からの政策提言―」など。
今、企業に求められているのは
「サバイバビリティ」と
「レジリエンス力」
おかげさまで「サステナビリティ未来会議」の対談はこれまでに8回を数え、ご好評をいただいております。本日は、このタイミングで改めて企業さまから教えていただいたことを振り返り、持続的な成長の実現を目指していらっしゃる企業さまに、今後の「鍵」となるご参考情報を研究者と投資家の視点から発信していけたらと考え、この分野の第一線でご活躍されている研究者お二人をお招きした次第です。鼎談に先駆け、お二人の簡単なプロフィールをご紹介させていただけたらと思います。まずは、慶應義塾大学総合政策学部教授の國領二郎先生。経営情報システムがご専門です。國領先生、本日はよろしくお願い致します。
よろしくお願い致します。
笹埜さんは、「サステナビリティ学」と申し上げていいのでしょうか、データガバナンスやESG(環境・社会・企業統治)戦略において先進的な研究に取り組まれていらっしゃいます。本日はそうした見地からのご意見を頂戴できればと思います。
はい、よろしくお願い致します。
早速ですが、本日の鼎談に当たり、これまでの8回の対談から学んだことを総括させていただきたいと思います。対談ではまず、その企業さまの「目指すべき会社の姿」をお伺いしました。その上で、そこに向けての経営トップのお考えや重要なSDGs課題と認識していること、それらを社内でどのように浸透させて取り組みを推進しているか、さらには実際の担い手となる従業員の方々の反応などもお話しいただきました。投資家の視点から、ご登場いただいた企業さまに共通して感じたこととして次の3つが挙げられます。
1つ目は、それぞれの企業さまが企業理念や経営トップの思いの下で、人財をとても大切にしていらしたこと。実際の担い手となる人財に企業理念や経営戦略をしっかり浸透させ、いかに目標の実現に向けて取り組んでもらうかをとても重要なことと考え、そのための施策、仕組み作りなどをされていました。2つ目が、統合報告書だけでは、その行間の意味することなどを読み解けないこともありますので、なぜサステナビリティが重要なのか(WHY)、どのようにその目標に向けて取り組んでいらっしゃるのか(HOW)などに加えて、その背景にある企業文化についても企業さまから直接お伺いすることで、これまで以上に企業の皆さまが生み出している社会価値と経済価値のつながりへの理解が深化したことです。
そして、最後の3つ目が、これらの結果として、その企業さまの持続的な成長ストーリーへの確信度の向上につながり得たということです。投資家としては、やはり中長期にわたり企業価値を向上させていく企業さまに投資したいですから、この持続的な成長ストーリーへの確信度は非常に重要です。こうしたことを踏まえ、國領先生、笹埜さんにご質問させていただけたらと思います。研究者と投資家の視点から今後の日本企業のSDGs活動の「鍵」を検証していくに当たり、まずは情報開示を含めた企業の持続的な成長への取り組みに関して、お二人が注目されている国際潮流や、欧米の最新動向についてお話しいただけますでしょうか?國領先生からお願い致します。

ちょっとどっきりする話から始めますが、2023年3月の米シリコンバレー銀行の経営破綻、そのスピードが目を引きました。何かが起こりそれが大事に至るまでのスピードがどんどん速くなってきています。このことは私の著書『サイバー文明論 持ち寄り経済圏のガバナンス』(日本経済新聞出版社)でも取り上げている「文明の転換点」の一つの表れだと思います。工業文明の時代には、綿密な計画を立てた上でノイズを排除しながら計画通りに物事が出来上がっていきました。
従って、財務の面でも成長性や効率性の指標を追いかければ良かったわけです。しかし今は、急成長を遂げている地域の中核バンクがあっという間に破綻してしまう時代です。そして、その展開の早さも従来では考えられないスピード感になっている。
背景には、ネットワーク化の進展でいろいろな場所での出来事が連鎖反応的につながって大事に至りやすい「複雑系」の度合いが高まっていることがあります。もう1つ、情報経済の特質として、ネットワークの外部性が働くとか限界費用が安いなど、これまでの工業製品市場とは違う強者の一人勝ちが起こりやすい構造になっていることが挙げられます。この2点から考えても、基本的にはマーケットは不安定な方向に向かいますし、ひと握りの人が書いたソフトウェアを何億人が使い、かつ生産コストは低いわけですから、内在的に貧富の差を拡大させる傾向を持っていることも事実です。
その結果、世界を見てもポピュリズム的な人気取り政策に頼らないと社会の不安が爆発してしまいかねない不安定な構造になっています。そうした中でも強いのは、例えば身近な飲食店なら、郊外の馴染みのお客さんがちゃんとついている店。一方で、人出の多さに頼って繁華街の路面でやっているような店はここ数年でかなり淘汰されました。大きな会社から小さな飲食店まで、今の時代に鍵を握るのはいかにサバイバルしていくか、いかにレジリエントであるかということかと思います。
そのためには株主だけでなく、従業員、顧客などから共感を得ていることが重要になります。コロナで閉まっていたが再開したらまた行きたいと思える店や働く人がまた働きたいという店と、2度と行きたくないという店、これは全然違います。今のレポーティングの仕組みがその辺りを的確に捉えているのかと言えば、いささか疑問です。取引規模額でマージンの計算をするといった従来型の会計システムだと、こうした企業の本当の価値を表現し切れていないのではないか。そこで今、試行錯誤しながら別のシステムを作ろうとしているわけですが、なかなかうまくいっていないのが現状です。
今、大きな時代の流れに関して國領先生が詳しくご説明くださったので、私は少し細かく、国際基準を作る潮流についてお話ししたいと思います。サイバー文明に突入し、マーケットが不安定になっている。私もこうした潮流がしばらく続くと見ています。そうした中で現状はパッシブ運用が主流になってきていて、継続的に利益を出し続けていくためには世の中の景気全体が良くなってくれないと困るということで、CSRの伝統を引き継ぐESG投資やサステナブル投資が出てきたわけです。しかし、株主至上主義からステークホルダー至上主義へと移り変わり、SDGsの17の目標とターゲットを経営に落とし込むためには、独自の、少し応用を利かせた指標、新しい会計基準が必要だろうという流れになっています。そうした中でIFRS(国際財務報告基準)財団の下でISSB(国際サステナビリティ基準審議会)が設立されていて、この動向に注目されている方も多いのではないかと思います。現状として、企業さまはGRI(Global
Reporting Initiative)などのガイドラインに基づいてこれを新しい会計基準の下に集約し、対照表などを出されているケースが多いと思います。
その中で私が取り組む「サステナビリティ学」、つまりSDGsを経営や教育に応用する学問の研究領域の観点から1つ面白いトピックをご紹介します。マテリアリティ(重要課題)の意味が変わってきているんです。マテリアリティという言葉は、SDGs経営の最初の方のキーワードとして出てきますよね。先ほど申し上げたGRIも、何でもかんでも開示すればいいというものではなくステークホルダーにとって大事な情報だけを取り込みましょうという意味で、このマテリアリティという言葉が使われてきたのですが、マテリアルなイシューズだったはずがマテリアルなインフォメーションへ、情報というものに対象が移ってきているんです。それによって齟齬を来して、ダブルマテリアルですとか、どこまでステークホルダーを絞り込むのかという問題が生じ、最終的には株主を中心としたステークホルダーの最終的な利益になる、あるいは将来のマイナスを防ぐためのサバイバビリティやレジリエンス力が高まるといった効果が出るのであれば、その限りにおいてISSBの要素を受け入れる流れに米国を中心になってきています。
しかし、ISSBが「マテリアル(Material)」という言葉を「シグニフィカント(Significant)」という言葉と同時に出してきていることで、戸惑われている企業のご担当者さまも多いのではないかと推察します。私は、これに関してはより解像度が上がったと評価しています。まずはサステナビリティに関するリスクや機会、つまりトピックを絞り込み、その取り組みについて重要な情報をいろいろと出す。
その中で、それが適切な情報なのかというところを「マテリアルな情報」と表現し、投資家の方々が「意思決定をしやすいような情報」に絞り込んで出していくということです。そこで重要になるのがエンゲージメントであり、ステークホルダーを取り込んだエンゲージメントのサイクルをPDCA(Plan・Do・Check・Act)サイクルで回せるようなデータ、ライフサイクルを社内、あるいはグループ内に構築しておくことがより求められる時代になるというように私は分析しています。
世界的にCSO、CSuOの重要性が
認識されてきた

お二人から大変興味深い大きな時代の流れや昨今の潮流などをお話しいただきました。この鼎談のお話は、企業さまへの示唆へと結びつけていけたらと考えておりますので、続いて、高い評価を得ている企業さまの事例から見えてきた共通点についてお伺いしたいと存じます。國領先生のお話を踏まえると、このご質問は、「どういった企業がサバイバルして、長期的に生き残れるのか」と言い直してもいいかと思います。この「生き残り」という言葉も「持続的な成長」という言葉に置き換えることも可能かもしれませんが、そうした企業の共通点としてどういったことが挙げられるとお考えでしょうか?
先ほど申し上げたことと重複するかもしれませんが、企業理念に対する共感を社会においてどれくらい得ているか。それには何のために情報開示をしているのかというところがポイントになってくると思います。従業員や顧客に直接的あるいは間接的に自分もエンゲージされている感覚を持ってもらうことで、企業が大変な時にサポートが回ってくるかどうかが大きく違ってくるように思います。
サステナビリティ対談に登場した8社さまのデータも拝見し、細かい点はたくさんありますが、総じて大事なことは意外にシンプルだという印象を持っています。先ほど私が「マテリアリティが変わってきている」と申し上げたことを面白いと思ってくださるとか、加藤さんとサステナビリティ対談で深い議論をされるような方々が社内にいらっしゃること、それが大切かと思います。世界的にCSO、CSuO(サステナブル経営推進責任者)の重要性が理解されてきています。
TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)は開示が必要な情報として4つの項目を示しています。1.ガバナンス、2.戦略、3.リスクマネジメント、4.指標及び目標です。ESGのガバナンスというのは、取締役レベルの方々がサステナビリティプランの策定から実行、その修正、改善、評価、そしてそれをさらにもう1度繰り返していくサイクルを見守る、あるいは責任を取る。そう紐付けられているところが本来のガバナンスだと思うので、TCFDでもこのようなフレームワークが出てきたのは納得感があります。ですから、ガバナンスがしっかりしている1つの指標としてCSOやCSuOの存在が挙げられます。もちろん企業によってはCHRO(最高人事責任者)がその役割を担ったり、サステナビリティ部署の部長さまや委員長さまがいらっしゃったりすることもあるわけですが。
私はこういった存在を社内で育成したり、採用できたりすることが大きな指標になると考えていて、投資家の方々の立場で考えたとしても、きれいなレポートを出すよりもはるかに重要と思うわけです。実践できているかどうかまではISSB基準では担保してくれませんから。
逆にガバナンスがしっかりしていないと、ディスクローズの質も悪くなってしまいます。そうした意味でも、どこにデータセンターやインフォメーションセンターを置くのかということを具体的に指示できる方が役員レベルにいないと、「CFOとCHROがあれこれやり取りして大変」といった状況に陥ってしまいます。やはり高評価事例の共通点としては、役員レベルでサステナビリティを愛するスキルの高い方の存在が欠かせないというのが私の率直な感想です。
おっしゃる通り、サステナビリティプランの実行や実践、それをどうやって担保していくのかは大変重要なポイントと思います。次のご質問では、先ほどお話しいただいた昨今の潮流を踏まえ、企業さまの持続的な成長に向けての課題とその理由についてお伺いできたらと存じます。これまでのお話の中で既に触れていただいたこともあるかと思います。その場合、この鼎談の読者の多くは日本企業に関係している方なので、欧米との比較で日本企業がより高く評価されるために何が重要かといった視点からお話しいただけたらと思いますが、いかがでしょうか?
結論から言うと、日本の企業はもっと積極的にアピールした方がいいんじゃないかと思っています。というのも、私の研究室の学生がずっとESGレポートの欧州と日本の比較をテーマに研究しているんですが、ビジネスモデルをしっかりリンク付けしようとする姿勢や熱意はむしろ日本の方が伝わってくるんですね。
欧州の企業のレポートは「社会的な義務としてしっかり履行しています」的な印象が拭えません。もちろん日本にもそういう企業がないわけではありませんが、真剣にビジネスと結び付けようとしている企業も多い。ひょっとしたらそれは根幹のビジネスモデルの転換を意味するかもしれないのですが、本当に真面目に取り組んでいるわけです。
しかしながら、残念なことにレピュテーションレベルでは欧州の企業にかなわない。やはり欧州の企業はアピールの仕方がうまいんです。
加えて、今はグリーンウォッシュの激しさが認識されたり、エネルギー価格の高騰であっさり目標を取り下げたりと、現実の壁にぶつかっているところも見受けられます。そこで1つハードルを越えていくには、本業のミッションをしっかり見直して、社会の中で自社のサステナビリティの価値を生んで高めていく努力が大切になります。それを真剣に行っている企業が評価されるべきですし、企業サイドはそこをもっとアピールしていいんじゃないかなと思いますね。

今、國領先生がおっしゃったように、グリーンウォッシュの問題など対応していかないとならない課題として、私が提唱しているのが「3つの罠」です。スタートアップ企業の三大障壁(魔の川・死の谷・ダーウィンの海)に引っ掛けたものですが、1つが時代遅れの者たちの川という意味の「恐竜の川(ダイナソー・リバー)」、それから「継続コストの谷」、そして最後が「ウォッシュ規制の海」で下手をすると深海まで引っ張り込まれる可能性があるぞと警鐘を鳴らしています。グリーンウォッシュは最後の海のところに該当します。
海外の情報の入手が遅れがちな企業さまは、この3つの罠を乗り越えていなかければなりません。ただし、サステナビリティのご担当者さまがいらっしゃる時点で、恐竜の川は越えていらっしゃるように思います。その次が先ほどの國領先生のお話にあったビジネスモデルとの紐付け、そしてそのアピールというところになってきます。ここがうまくいかないと、ステークホルダーの絞り込みができていない状態でサステナビリティレポートに何でもかんでも盛り込んでしまう状態が続き、それこそ200ページ、300ページにも上るレポートを毎年アップデートしていくことになります。最初は大手コンサルティング会社などに依頼して、高いお金を払ってきれいなものができたと安心されたかもしれませんが、毎年それが続くと、どうやって費用対効果を証明していくんですか、というツッコミに答えていかなければならなくなります。
こうした継続コストの谷を乗り越えるには、やはり日本企業が得意としているビジネスモデルとの連携により戦略的にSDGs活動を行っていく必要があります。
最後のグリーンウォッシュもその延長線上にあると考えています。有名投資家のウォーレン・バフェット氏は「潮が引いた時、誰が裸か分かる」という名言を残していますが、企業側もエンゲージメントやコミュニケーションの対象を絞っておかないと、後々グリーンウォッシュ、SDGsウォッシュ、ESGウォッシュと言われかねない懸念があります。それを回避するには、継続コストを下げていくというところから既に戦いが始まっていて、そこさえ乗り越えれば、ウォッシュ規制もうまく乗り越えていけるのではないかと思います。
低PBR企業への改善策要請は
「エクスプレイン」再考の好機?
ありがとうございます。情報開示が目的になってしまってはいけないというお話ですね。私たちは投資家として毎年重大なESG課題をレビューして決めていますが、5つある重大なESG課題のうちの1つがまさに情報開示でして、企業さまとエンゲージメントする際に「情報開示の拡充を期待しています」というお話をさせていただく時もあります。
このような時、今、笹埜さんがおっしゃったように、私たちも情報開示が目的でとどまっていてはいけないと考えています。情報を社外に開示するためには社内でのさまざまな議論やコンセンサス作り、意思決定などが必要となり、持続的な成長の実現に向けた課題に対してどのように考え、実践していくかがポイントになります。私たちが情報開示を重大なESG課題と位置付けている背景には、このように情報開示が社内の検討やその実践を促すきっかけになることを期待したい思いがあり、同じ目線からご指摘くださった笹埜さんのお話を大変興味深く拝聴した次第です。國領先生からは、ビジネスモデルとの紐付け、そして、その真剣さなどをもっとアピールしていくことが重要であるといったキーワードを幾つか頂戴しました。
次のご質問は、日本企業があまり評価されていないという國領先生のお話につながる部分があるかとも思いますが、2023年2月に東京証券取引所(東証)が「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた要請」として、PBR(株価純資産倍率)が1倍を割れている企業に改善計画の開示を求める方針を示しました。企業さまにとっては大きな関心事かと思い、これに対するお二人のお考えをお伺いできますでしょうか?
バブル崩壊後の日本経済の失われた20年だか30年だかの影響もあり、日本では寝かせている資産が多過ぎることに根本的な問題があるように思います。資産をうまく活用できていないのに加え、ビジネスモデルも旧態依然たるまま。PBR1倍未満の上場企業が増えているのは、そうしたことによる弊害の1つの表れじゃないかという気がします。同情論を言えば、バブルが弾けて以降、クッションを厚く持っておかないといざという時に大変なことになるという警戒心が芽生え、海外からは贅肉と揶揄されるような分厚い不稼働資産を持ち続けてきたのが原因でしょう。
一方で、最近の雇用状況に目を移すと、ここ数カ月のシリコンバレーのレイオフの激しさは「今までこんなに儲かってきたのにここまでやるの?」というくらいドライですよね。本来ならば社会全体で失業率を十分低く抑えて移行に伴う痛みが吸収できればいいのでしょうが、実際にレイオフに巻き込まれた人のSNSなどを見ると、相当な社会的痛みを伴っているのは間違いない。そうした中で今回東証の話が出てきて、「ちょうどいい加減というのは一体どの辺りなのだろう」と思いながら報道記事を見ていたところです。米国流のやり方をそのまま日本に持ち込むのがいいのかどうかは正直疑問です。日本の場合、地方のシャッター商店街の店主も実際のところ必ずしも困ってはいない場合があるという妙な状況になっています。家賃収入が入ってくるから商売しない方が楽ということになる。
今は資産収益率が低くても大丈夫かもしれませんが、今後は金利が上がってきますから、深刻な問題を起こしかねない。そこは早期に活性化していく必要があります。
PBRが1倍を割っていることから考えられるのは、市場の信頼が低下している。あとは資本効率が非効率的だと評価されている。そうした投資家からの評価が大きく影響しているのではないかと思います。「コンプライ(遵守)・オア・エクスプレイン(説明)」というそもそもの原則に立ち戻れば、今回の東証の要請は理に適っているのではないでしょうか。
私自身、英国発祥のこの原則のうち、「エクスプレイン」があまりにも米国ひいては日本に引き継がれていない点を懸念していました。全面的に従うのか、はたまた全部退けるのか。やはりそのディスカッションというかエンゲージメント、シナリオをきっちり構築していくことが本来は求められていると考えていて、今回の要請はそのいい機会として活用していただければと思います。今回の要請により企業さまが改善計画を策定し情報開示することは、少なくとも3つの良い影響があるのではないかと考えています。
1つはデータの収集やシステムの再構築など情報開示をする上で一時的に運用管理費は増加するかもしれませんが、半面、それが信頼の獲得につながり、不安定な市場において持ちこたえやすい状態になっていると見てもらえる可能性があるということです。
2つ目は、その開示によってどういうシナリオを描いているか、会社の将来像をしっかりエクスプレインできれば、再評価されるかもしれないということ。要は1つ目と同様、信用リスクを下げるチャンスなのではないかと思うわけです。
3つ目は投資家やアナリストの方々はロングタームで企業分析をする傾向にあり、そうした方々が納得できる合理的なシナリオを描いていれば、最終的には評価してもらえる可能性が高まるということです。財務的な数字だけでは分からない、例えば「人的資本への投資です」とか「将来的な環境負荷軽減のための技術、知的財産に対する投資です」といった注釈の形で財務的な数字にインテグレートすれば、プラスに作用するのではないかと考えています。企業が今、長期的な視点から経営判断を見直し、戦略を立て直すという観点からはいい契機となるのではないかと思います。
國領先生からはレイオフに遭った方やシャッター商店街の店主の方といったリアルな手触り感のあるお話を頂戴しました。また、笹埜さんが指摘されたエクスプレイン・ディスクロージャーの重要性もその通りだと思います。あっという間にお時間も過ぎ、これが最後のご質問となります。情報開示の現状や評価を踏まえ、今後の日本企業のSDGs活動の「鍵」や目指すべき方向性についてお話しいただけたらと思います。
先ほど笹埜さんが言ったことが結論ではないでしょうか。やはり対話をどうするかがポイント。各企業がいろいろなストーリーを持っているわけです。「当社はこういう形で世の中に貢献していきたい」、「従業員にとっても働きやすい会社でありたい」といったビジョンがあり、それを具体的にどう実現していくかについての説明を行い、そこへの共感を得ていく形です。
その際は、市場関係者だけでなく、社会の支持を得ることが大変重要になります。ポジティブなメッセージがない企業は、さまざまなショックや攻撃に対して脆弱になりがちで、それはリスクファクターとして投資家にもネガティブなイメージを与えるでしょう。
ですから、企業は自社のパフォーマンスとソーシャルグッドの両立を目指していく必要があり、そのことが冒頭で申し上げた不安定な時代にサバイバルしていく上での安定性につながるわけです。そうした理想の実現に向けては、これまでよりはるかに多くのステークホルダーを意識しなければなりません。そうしたステークホルダーとの対話と共感を大事にする経営が求められているように思います。
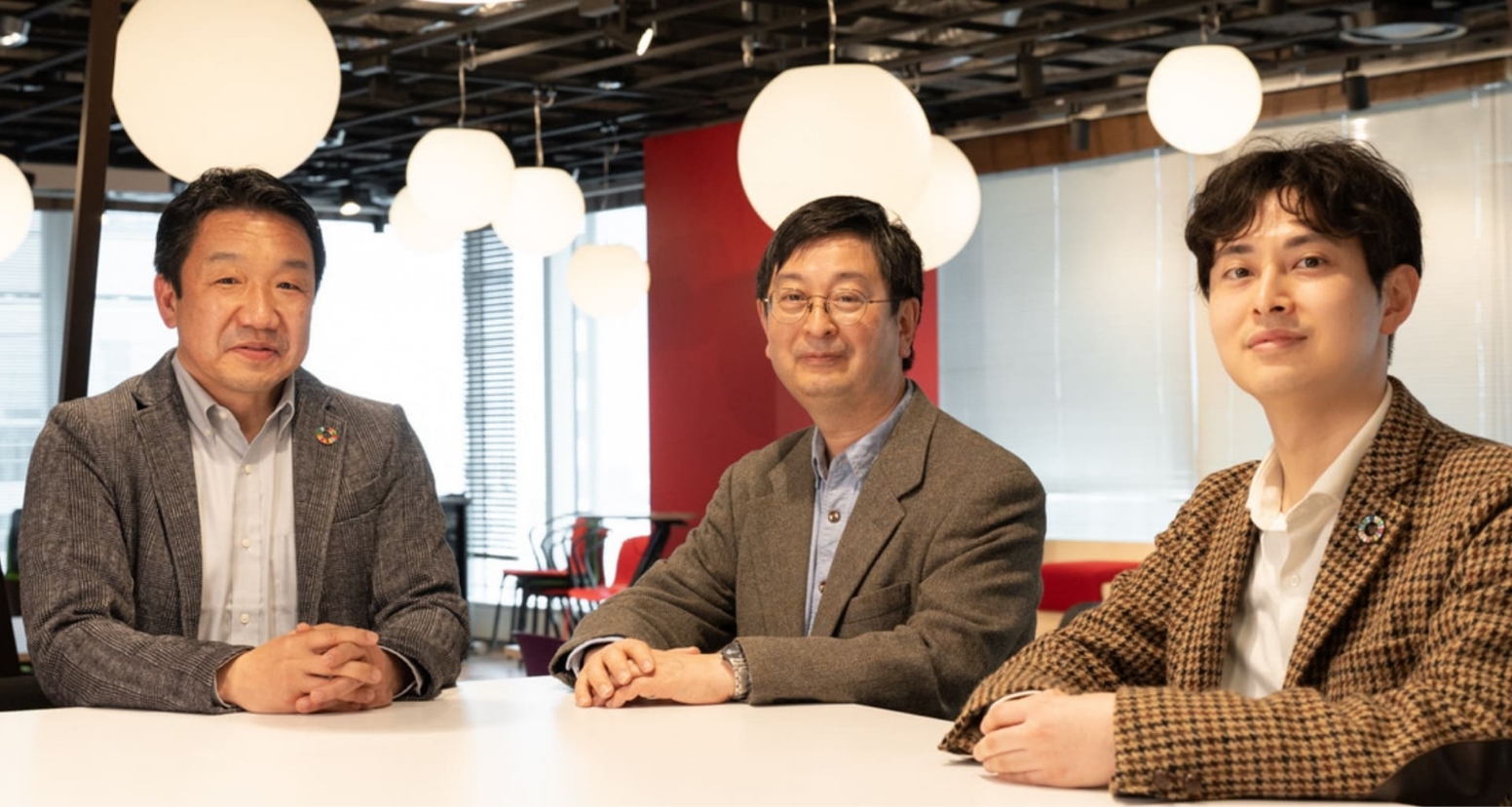
実証された
「ステークホルダーとの
対話の重要性」
國領先生のご専門である経営情報システムの観点からステークホルダーとの対話をご覧になるといかがでしょうか?
少々テクニカルな話になってしまうんですが、POSレジってありますよね、あれがなぜ偉大な発明だったかというと、直接業務であるモノを売る行為と間接業務である記録する行為を一体化したからなんです。
目の前の客のバーコードを読み取り終えるまでは次の客の読み取りができない、言い換えれば販売記録のレポーティングを終えるまでは次の客の相手ができない仕組みを作り、なおかつ代金を受け取ってキャッシュレジに入れるまでの手間も数十秒から10秒程度に短縮しています。
直接業務の負担を軽減しながら、直接業務と間接業務を一体化したのがPOSレジの功績で、同様に、今のセンサー技術やネットワーク技術を駆使すれば、オペレーションしながらカーボン排出量のモニタリングができるようになってきているんです。対外的に公開するデータが自動的に取れていくような仕組み作りを目指していくといいんじゃないかなと思いますね。
なるほど、そうした仕組み作りも企業さまの今後の「鍵」になりますね。さて、先ほど國領先生がおっしゃった「ステークホルダーとの対話が重要」というご指摘に関連するお話に戻させていただくと、「投資家と企業との対話は本当に効果があるのか?」というご質問をいただくことがあります。そうしたご質問への1つの回答として、私たちが実際に対話を行った事例を用いて、その効果を、具体的には企業さまが改善された課題の定量分析を実施し、結果をご説明しています。実際に対話を始めて1年目に課題が改善した数は、明確に確認できるまで至りませんでした。
しかし、その後2年目、3年目、4年目と年数を重ねるにつれ、それに比例して課題が解決した件数が増えていることを確認できました。投資家としても企業さまとの対話はとても重要だと考えていますが、実際の対話で改善につながった効果が確認できましたので、この定量分析の結果も踏まえて、今後も積極的に対話を推進していきたいと考えています。笹埜さん、今後の「鍵」、目指すべき方向性についてはいかがでしょうか?
サステナビリティ・ディスクロージャーとは、会社の未来を語ることだと思います。加えて、國領先生のご専門である経営学と私が学んできた法学や国際関係論の関連性がよく見えてきている時代であることを踏まえ、これからの戦略を語っていく必要があると考えています。例えば、SASB(米国サステナビリティ会計基準審議会)は当初、米国の公認会計士が集まったカリフォルニアのNPO法人でした。そこから、経営学的には「戦略的提携」ということになるかと思いますが、英国のIFRS財団の下でISSBとして統合されて今のように大きくなりました。言うなら、サステナビリティ・ディスクロージャーに関するソフトローはこうした非営利法人が担ってきたわけです。営利法人でも例えば英国に本社があるユニリーバ社は人的資本も含めかなり先進的な取り組みをされていて、米国でもケーススタディの対象となってきました。
こうした国家、法的機関以外の存在がルールを作り上げ、それが市場の目にさらされるというところでいくと、先ほどの「会社の未来を語る」もそうですが、テキストデータというものが技術的により重要になってくると思います。最近なら、今巷で話題の「ChatGPT」、こうした大規模言語モデル(LLM)を活用して、パーソナルAI(人工知能)エージェントのように情報を入れれば入れるほど自社に最適なサステナビリティ情報を出してくれるというような、従来モデルとはだいぶ違った情報検索システムが出てきているので、そうしたところにも注目すべきでしょう。
私が研究するサステナビリティ学の観点からは、エンゲージメントを取るべきステークホルダーが未だに広過ぎるところは広過ぎる半面、狭いところは狭いという結構なムラがある中で、これから特に強化すべきなのは従業員とのエンゲージメントだと思っています。「それがないと途中で止まってしまう」と、経営陣の方々と現場の従業員との間に立って苦労されているサステナビリティ部署の管理職の方々が何人もご相談に見えていて、エクスターナル(社外)とインターナル(社内)、両方のエンゲージメントの必要性を日々痛感しています。エクスターナルの方では海外への発信も非常に重要です。JPX(日本取引所グループ)や金融庁などは海外への発信として外国語による統合報告書を推奨しています。方向性はいいのですが、そもそも文化が違いますし、統合報告書のフォーマットやテンプレートも違いますから、いかにして文化的な面も含めてしっかり浸透させていくかがエンゲージメントではないかと思います。
プロセスとしては「エンゲージメントした上でのディスクローズはエクスプレインにつながる」という理解に向かっていく必要がある。そうしたインフォメーションのサイクルを確立していく意味でも、技術的には先ほど申し上げたテキストデータの有効活用技術を推進されるといいのではないかと思いますね。
今のお話、私どもも投資家としてAI機能を用いてテキストデータを読み、企業評価に反映し始めているところで、改めてその重要性を感じた次第です。「従業員とのエンゲージメントも重要」とおっしゃいましたが、実際に戦略や施策を実践するのは従業員の方々ですから、従業員の皆さまのモチベーションを高め、全社一丸となって目指す方向に向かっていく体制作りは私たちも本当に重要と認識していまして、企業さまともよくお話をさせていただいております。
お二人の総括を受けて、僭越ですが、最後に私の方からサマリーのコメントをさせていただきます。投資家の視点から、これまでのサステナビリティを巡る動きを改めて振り返ってみますと、コーポレート・ガバナンスコード(企業統治における行動規範)が制定されて東証の上場会社に適応され、その結果、社外取締役が増え、取締役会の構成が多様になったり、非財務情報の開示や統合報告書の拡充が進んだりと、望ましい変化が生まれているのも確かです。
その一方で、先ほどのPBR1倍割れの企業が未だ多いとか、ROE(自己資本利益率)の水準がなかなか向上していかない企業が散見される状況にあることも事実です。この状況をどう考えるかですが、例えば、社外取締役などは、本質的に期待されている機能や役割を発揮するまでに至っておらず、形式的な変化にとどまっているのではないか。それらがこのPBR1倍割れ、ROEが上がっていかない状況の1つの要因になっているようにも考えられ、今後は、形式よりも中身、その実質が今まで以上に重視されるフェーズになっていくように思います。そして、株主の代表として企業価値の最大化の実現に携わる社外取締役への期待が今後さらに高まっていくのではないでしょうか。
加えて、企業さまには持続的な成長に向けて本質的な機能の強化や期待役割の促進、その状況も踏まえた「エクスプレイン」を深化し、ステークホルダーとの対話を重ねていただくことで、投資家の理解も深まっていきます。
理解が深まればそれだけ持続的な成長ストーリーへの確信度が高まります。投資は将来に向けたものなので、この確信度というのが非常に重要です。本日お二人から教えていただいた今後の「鍵」も企業さまにお伝えし、企業さまと私ども投資家との相互理解を深め、将来的な企業価値の向上に貢献していけるよう尽力していきたいと考えております。本日は誠にありがとうございました。

三菱UFJ信託銀行
サステナブルインベストメント部
フェロー・加藤正裕
慶應義塾大学経済学部卒業後、三菱UFJ信託銀行入社。米国三菱UFJ信託銀行含め、国内外の運用関連部署でアナリスト、ファンドマネージャー業務を担当。2005年から責任投資に従事。国連「責任投資原則」日本ネットワーク共同議長として責任投資の普及・推進に尽力、個人および年金向け責任投資プロダクトの開発、国内外株の議決権行使・エンゲージメント実務にも携わり、近年はグローバルなESG・機関投資家の動向調査等をロンドンで担当。2019年からは東京でサステナブル投資の企画・推進に従事。2023年4月より現職。
