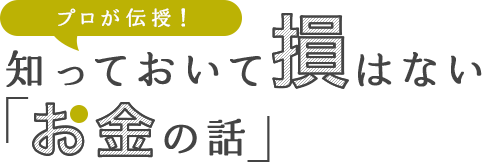コラムVol.121 長期投資と短期売買(前編)

- 正岡 利之 (まさおか としゆき)
- 日本証券アナリスト協会検定会員。行動経済学会会員。
1982年三菱信託銀行(当時)入社。1985年より一貫して運用業務に従事し、2018年から2022年3月の退職までMUFG資産形成研究所長を務める。
内外債券のファンドマネジャー、国内株式のリサーチ、年金資産の運用管理、また投信会社での運用や商品開発など、運用に関する幅広い経験を有する。
長期投資と短期売買(前編)
資産を現預金だけに置いておくと、物価が上昇した時に資産価値が実質的に減価します。そこで株式などへの分散を検討することになります。株式の時価総額は長期的に成長を続けているので、銘柄分散した複数の株式を長期に渡って保有することで、その成長の恩恵を期待するのです。
しかし長期投資であっても、実際に始めると価格の動きが気になりだすものです。そこで本コラムでは、短期的な売買を行う場合と長期投資による資産の成長を目指す場合とを比較し、価格の動きに対する考え方について2回に分けて考察してみたいと思います。前編の本稿では、「有価証券を買い付けるとき」の価格の動きに対する考え方について取り上げます。
有価証券を買い付けるとき
最初に、短期的な利益狙いの売買について考えてみます。ある銘柄を買おうと心に決めて価格の動きを見ていると、目の前でじりじりと上がっていくことがあります。割り切って早いうちに買えてしまえば良いのですが、最初の安い価格を覚えているので、高くなった価格でなかなか買うことができません。
買い付けは慎重に、という趣旨の格言があります。慎重に、かつどこかの地点では最初の一手を打ってみることも大切です。
行動を起こさないで、気迷いながら様子を見ていると、価格が上がるにつれて周囲の人たちも強気になってきます。自分自身に買いたい気持ちが残っていると、焦燥感に駆られて最後は買いに走ることになりかねません。
そんなときは、往々にして高値であることも多いものです。買いたい人が大方の買いを済ませて、みんながポジションを持った(株式などの有価証券を保有した)状態になると、多くの人たちが強気になります。もうそれ以上に買う人がいなくなると、その時が相場の天井かもしれません。
「人のいく裏に道あり花の山」という格言があります。人々が買いたがっているときに売ってあげて、売りたがっているときに買ってあげる。逆張りの発想ということもできるでしょう。事後的に相場を振り返ればたしかに格言の通りです。実際にこれができると収益も増えます。
しかし現実には、その最中になかなか冷静・客観的になれないことも多いと思います。焦燥感に駆られたりせず、自分自身の状態を見極めながら、価格の動きを的確に予測することができるかどうか…
このような価格に着目した短期的な売買にトライすることから、学ぶことも多いと思います。ただし、そう簡単なことでもありません。「投資」という言葉から、このような難しい短期売買のことを連想する人も多いようです。
一方で、長期投資は、短期的な価格の上下の波をいくつも乗り越えたところにある、長期的な成長による利益を得ようとするものです。価格が高くなったときに利益を得ることを目的として、低いところで買い付けておこうなどと、短期的な価格の動きに一喜一憂する必要はなくなります。
目線は長期的な利益にあるので、短期的な価格の波が上げても下げても、有価証券を保有したままで良いことになります。安値で買い付けることができなくて、買い付けた後で価格が下がっても、保有したまま波の上下に身を任せて、たゆとうていれば良いのです。
予定した金額を1度に投資することが心配であれば、何回かに分けて買い付ける方法もあります。さらに買う頻度を増やしていくと、積立投資になります。積立投資は、短期的な価格の上下で儲けようとするものではなく、価格の波の中で買い続けることで、より将来の成長を得ようとするものです。