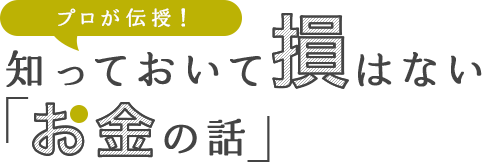コラムVol.189 マネーライターの取材裏話――マネー誌に書かなかったこと&書けなかったこと 2025年「年金改革」、「転ばぬ先の杖」の対策を考えよう!

- 森田 聡子 (もりた としこ)
- 早稲田大学政治経済学部卒業後、地方紙勤務を経て日経ホーム出版社、日経BPにて『日経おとなのOFF』編集長、『日経マネー』副編集長、『日経ビジネス』副編集長などを歴任。2019年に独立後は書籍や雑誌、ウェブサイトなどで、幅広い年代層のマネー初心者に対し、難しい投資・税金・保険などの話をやさしく、分かりやすく「書く」(=ライティング)、「見せる」(=編集)ことをモットーに活動している。著書に『節税のツボとドツボ』(日経BP)、編集協力に『マンガ 定年後入門』(日本経済新聞出版社)、『教科書には書いてない 相続のイロハ』(日経BP)。
見送られた「国民年金3割底上げ」
国会では衆議院で与党が15年ぶりに定員の半数を割り、連日、緊迫した論戦が繰り広げられています。そうした議論の重要なテーマの1つが年金改革関連法案です。
2024年は5年に1度、定期健診のような形で年金財政をチェックする「財政検証」の年でした。そして、2025年からはその検証結果に基づいた「年金改革」が行われていきます。
「年収106万円の壁」をなくし、社会保険の適用範囲を拡大する。厚生年金保険料の“労使折半”ルールを見直し、企業側が多く負担できる特例措置を導入する。稼ぐ高齢者の厚生年金を減額する「在職老齢年金」を見直し、高齢者が働きやすくする……。数々の改革が実施されることになりそうですが、そうした中で少々わかりづらいのが「国民年金(基礎年金)の3割底上げ」です。
端的に言えば「厚生年金の積立金を活用して国民年金の将来的な給付水準の低下を防ぐ」ものですが、会社員からすれば「自営業者の年金が危機的なのはわかるけど、会社員の年金から穴埋めするのは理不尽!」と感じるかもしれません。
しかし、世間の反発が大きかったようで、「令和7年度税制改正大綱」に盛り込まれたものの、2025年1月末には厚生労働省が実施判断を次回の財政検証(2029年)まで先送りすると言い出しました。
ただ、この問題はもう少し別の角度からも考えてみる必要があるように思います。
「小泉改革」で大きく変わった日本の年金制度
改革案の背景を理解するには、公的年金制度の「小泉改革」まで遡る必要があります。
「小泉」と言っても2024年秋の自民党総裁選で年金改革案を提唱した進次郎議員ではなく、先代の純一郎元首相の方です。
少子高齢化の進行で現役世代が高齢世代を支える年金制度の維持が難しくなる中、2004年には政治家の年金保険料未納問題が発覚し、年金制度への不信感が一気に高まりました。そのタイミングで当時の小泉純一郎政権が断行したのが、「100年安心」を掲げた抜本的な国の年金制度の見直しです。
目標としたのは、厚生年金のモデル年金(平均的な月収〈賞与も含む〉を得ながら40年間厚生年金に加入した会社員とその専業主婦〈夫〉の配偶者が受給する年金)の給付水準が、現役世代の平均手取り収入の50%以上を維持することです。
そこに向けては現役世代の保険料を上げざるを得ませんでしたが、保険料には上限(保険料率18.3%)を定めて上昇に歯止めをかけました。さらに、国民年金の国庫による負担を2分の1まで引き上げました。そして、年金に積立金方式を採用し、その運用を行う年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)を立ち上げました。
その上で、おおむね100年後までの給付を保険料や積立金などの範囲内で賄うことを前提に、給付を調整する仕組み「マクロ経済スライド」を導入したのです。これにより、従来は物価や現役世代の給与水準に連動する形だった年金額は、現役世代の人数の減少や平均余命の伸びなどを考慮して抑制されるようになりました。
「マクロ経済スライド」による年金カットが終わらない
マクロ経済スライドによる給付水準の抑制は、国民年金と厚生年金で別途行われており、それぞれの年金財政が健全化するまで続きます。2004年の当初のシナリオだと、国民年金も厚生年金も2023年には健全化するはずでした。
しかし、国民年金は保険料の未納者や減免・納付猶予制度の利用者がいることから健全化のペースが遅く、2024年の財政検証では過去30年並みの経済成長を想定した場合、なんと2057年までマクロ経済スライドによる調整が続くという試算が出てしまったのです(ちなみに、厚生年金の方は同じ試算で2026年には調整が終了します)。
このスケジュール感だと、調整期間が長引く国民年金は現状よりも3割ほど受給額が減ってしまいます。ご存じのとおり、国民年金はもともと少額ですから、さらに減額されたら国民年金頼みの自営業者やフリーランス、専業主婦(夫)などは大きな打撃を受けます。
そこで、厚生年金に助けてもらって国民年金と厚生年金の調整終了時期を一致させようというのが今回の改革案でした。
収入が少ない会社員や若手会社員には朗報!
改革案に話を戻します。少々直截的な表現になりますが、この改革で誰が幸せになるのかと言えば、まず想定されるのは自営業者やフリーランス、そして専業主婦(夫)などです。
一方で、国民年金は会社員も受け取っています。会社員でも現役時代の賃金が低めだと将来受け取る公的年金に占める国民年金の比率が高くなります。改革は、そうした人にとってもウェルカムと言えそうです。アルバイトやパートで厚生年金に加入している人も同様です。
さらにもう1つ、改革案にはマクロ経済スライドによる調整を終えることが明記されており、調整期間が終われば年金額は物価や現役世代の賃金に合わせて上昇していくようになります。とすれば、それ以降に年金を受給する世代にとっても悪い話ではないはずです。
逆に、この改革が逆風となるのはどんな人でしょうか?
現在年金を受給している世代は長期のデフレのおかげでマクロ経済スライドが発動しなかったわけですから、ある意味、“もらい過ぎ”という見方もできなくもありません。しかし、厚生年金をもらい始めたばかりの人やこれからもらい始める人は、改革の負の影響をもろに受けることになります。
ましてやここ数年は驚異の“値上げラッシュ”です。物価高下の年金暮らしの過酷さは近年ニュース番組などでも繰り返し取り上げられ、SNSには「とても他人事とは思えない」、「老後資金2000万円ないと、ああなるってこと?」といった反響が多数寄せられています。
お金に働いてもらうならiDeCoよりNISAがお勧め
2029年の財政検証がどうなるかは分かりませんが、日本の経済が大きく成長して年金財政が画期的に改善しない限り、またぞろ同じ問題が持ち出される可能性が大です。逆風を受けそうな世代は「転ばぬ先の杖」で対策を考えておきたいところです。
完全リタイアのつもりだったけれど、健康維持のためにもアルバイト程度の仕事をする。それも1つの方法です。
あるいは、インフレ対策も兼ねて株式や株式投資信託などでの運用を継続する。こちらは、“お金に働いてもらう”という考え方です。ただし、現役バリバリの頃のように投資する期間や余裕資金がたっぷりあるわけではないので、保有資産のどれだけを投資に回すのかは慎重に考える必要があります。自分で判断するのが難しければプロに相談してもいいでしょう。
今国会ではiDeCo(個人型確定拠出年金)の改革案も取り上げられ、拠出額の上限が大きくアップしたり、運用可能年齢が70歳まで引き上げられたりしそうです。しかし、iDeCoは先の改革案による年金減額の対策にはあまり向いていないように思えます。
iDeCoの場合、受け取り時には一括なら退職所得控除、年金形式なら公的年金等控除が適用できますが、控除の上限を超えた分は課税対象になってしまうためです。また、受け取る度に手数料がかかり、残高があるうちは口座管理手数料も徴収されます。
むしろ、枠が余っているのであれば、新しい少額投資非課税制度(NISA)の利用を検討したいところです。売却益は非課税ですし、年齢や期限を気にせず運用を続けていくことができます。