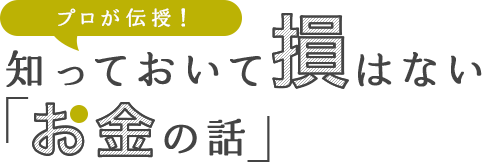コラムVol.194 マネーライターの取材裏話――マネー誌に書かなかったこと&書けなかったこと DC加入者も注目!バージョンアップ「iDeCo」との付き合い方

- 森田 聡子 (もりた としこ)
- 早稲田大学政治経済学部卒業後、地方紙勤務を経て日経ホーム出版社、日経BPにて『日経おとなのOFF』編集長、『日経マネー』副編集長、『日経ビジネス』副編集長などを歴任。2019年に独立後は書籍や雑誌、ウェブサイトなどで、幅広い年代層のマネー初心者に対し、難しい投資・税金・保険などの話をやさしく、分かりやすく「書く」(=ライティング)、「見せる」(=編集)ことをモットーに活動している。著書に『節税のツボとドツボ』(日経BP)、編集協力に『マンガ 定年後入門』(日本経済新聞出版社)、『教科書には書いてない 相続のイロハ』(日経BP)。
年金改革関連法案審議が大幅に遅れた理由
2025年は年金改革関連法案の国会審議が大幅に遅れました。3月のはずだった国会への法案提出が行われたのはなんと5月16日。しかも、与党・自由民主党がいったん法案から削除した「年金の底上げ」が、野党第一党の立憲民主党の提案を受け4年後の年金制度の財政状況の検証を踏まえて判断するよう修正されるなど、ごたついた印象は否めません。
年金の底上げとは、過去30年間と同様の経済状況が今後も続いた場合に2057年度の国民年金の給付水準が3割近く減ってしまう恐れがあることが分かり、比較的財政に余裕のある厚生年金の積立金を活用するなどして給付水準の維持を目指す案です。この3割削減の影響をもろに被りそうなのが非正規雇用の多い就職氷河期世代で、自民党による法案からの除外は「氷河期世代を見捨てた」と批判を浴びました。
しかし、厚生年金の積立金を使うことには厚生年金加入者や労働団体などから反発もあり、世論調査を見ても底上げ案への賛成と反対の数は拮抗しています。与党からすれば、7月の参議院選挙を控えてこうした厄介な法案は扱いたくなかったのが本音でしょう。
実はiDeCoも変わります!
年金底上げを巡る論戦や駆け引きの陰に隠れた感はありますが、この年金改革関連法案の中には昨年来話題になっていたiDeCo(個人型確定拠出年金)の改革案も含まれています。よって、今後は2024年のNISA(少額投資非課税制度)に続いてiDeCoも大きく変わっていくことになります。
勤務先で企業型DC(確定拠出年金)に加入している人は「iDeCoなんて関係ない」と思っているかもしれませんが、そんなことはありません。
そこで今回は、iDeCoのアップデート内容と、新iDeCo活用の注意点をご紹介していきます。
iDeCoの掛け金の上限額が大きくアップ
注目されるのは、iDeCoの掛け金の上限額が大きくアップすることです。
自営業者や専業主婦の場合、現行では月額6万8000円が同7万5000円(国民年金基金の加入者は基金との合計)まで拠出することができるようになります。
会社員の場合は、勤務先に企業年金制度があるかどうかによって上限額が変わります。
企業年金がない会社員だと、月額2万3000円の上限が一気に同6万2000円まで拡大します。企業年金がある会社員や公務員の場合は、月額2万円の上限がやはり6万2000円に引き上げられますが、企業年金や企業型DCの枠が優先されるため、残りが実質的なiDeCoの上限額となります。
なお、改正で企業型DCの従業員による上乗せ分「マッチング拠出」の制限(企業の拠出額を超えられない)も廃止されるので、マッチング拠出についても先の月額6万2000円の上限や企業年金の掛け金に配慮しながら増やすことができるようになります。
満70歳になるまで条件付きで加入可能に
iDeCoは老後に向けた資産形成のための制度ですから、加入や引き出しができる年齢は制限されています。改正により、こうした年齢制限も変わります。
現行制度では、公的年金制度の加入者であれば、満65歳に達するまでiDeCoの加入、積み立てができます。70歳までの就業機会確保が努力義務となる中で、iDeCoも条件付き(iDeCoの加入者や運用指図者だった人、または、DCの財産をiDeCoに移換できる人)で、満70歳まではiDeCoの加入が可能になります。
ただし、国民年金の老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給していると加入はできないので、注意が必要です。
iDeCoにあってNISAにないメリット
勤務先でDCに加入している人は、あえてiDeCoに加入する必要性を感じないかもしれません。老後資金の上乗せも、つみたてNISAで十分じゃないかと思いますよね。
老後の資産形成を前提にした場合、NISAとの比較でiDeCoが優れているのは、拠出した全額がその年の所得から控除され、その分、所得税や住民税が軽減されることです。
iDeCoの上限がアップしたことで節税額も大きく増えます。たとえば、前述のとおり、企業年金制度のない会社員は現行の拠出上限額が月額2万3000円、改正後は同6万2000円です。年収800万円の会社員(所得税率20%、住民税率10%)が限度額まで拠出を行ったとすると、控除額は8万2800円(2万3000円×12カ月×30%)から22万3200円(6万2000円×12カ月×30%)へ、1年で14万400円も多くなります。
所得税率は高所得者ほど高くなり、それが控除額に反映されます。加入期間が20年、30年と長くなるほど累積控除額が増えていくことを考えると、この節税効果は侮れません。
また、仮にこの先転職して転職先に企業型DCの制度がなかった場合、それまでDCで積み立ててきた分をiDeCoの口座に移換することもできます。
企業型DCとiDeCoで運用対象を分散しよう
この記事を読んでくださっている方は、企業型DCとiDeCoを併用されるケースが多いのではないかと思います。
たとえば、企業型DCでTOPIX(東証株価指数)に連動するインデックスファンドを指定している人が、iDeCoでも日本株のインデックスファンドを指定したら、ファンドの銘柄や運用会社は違えど値動きはほぼ一緒ということになります。
この先、海外の株式市場が総崩れし日本市場だけ独歩高といった展開を確信している方なら話は別ですが、いくら「長期」で「積み立て」とは言え、一極集中型の投資はあまりいい結果を招いていません。
iDeCoも企業型DCも運用商品は原則35本以内と規定されています。iDeCoの運用商品は取り扱う金融機関によって異なりますが、企業型DCより選択肢が豊富なケースが多いようです。新たにiDeCoの利用を考える際は、運用先分散を意識したいものです。
“市場のクジラ”GPIFのポートフォリオが参考になる
参考までにご紹介したいのが、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)のポートフォリオです。
GPIFは厚生年金や国民年金の積立金の管理・運用業務を担う機関。取り扱い資産は世界最大級の160兆円超に上る“市場のクジラ”的な存在で、銀行や証券会社、商社、不動産会社、シンクタンク、官公庁などから運用のプロが集まっています。
そんなGPIFの現在の基本ポートフォリオは、「国内株式」「国内債券」「外国株式」「外国債券」がそれぞれ25%というもの。あまりのシンプルさに拍子抜けされた方も多いのではないかと思いますが、2021年度は5.42%、2022年度は1.50%、2023年度に至っては22.67%と決して悪くない収益率を残しています。
この収益率の推移を見れば、運用対象分散の効果が実感できるのではないでしょうか。
今後は“おまけのサービス”が充実してくる!?
長期目線ではGPIFのポートフォリオを頭に置きつつ、もっとリスクを取れるなら外国株式や国内株式の比率を高めていくのも1つの方法です。
その際に気を付けたいのが手数料。運用が長期に渡ることを考えれば、NISA同様、同じ運用対象なら信託報酬の安い投資信託を選ぶのが鉄則です。
企業型DCと違ってiDeCoには口座開設手数料や運営管理手数料がかかります。手数料の額は金融機関によって異なりますが、運営管理手数料は将来積立金を受け取る期間中も徴収されますから、使いやすさや商品ラインアップなどを確認した上で、なるべくリーズナブルな手数料の金融機関に口座を開設しましょう。
iDeCoの積み立てでポイントが貯められる金融機関も増えています。今回の改正で今後はさらに充実しそうな、こうした“おまけのサービス”にも注目したいところです。