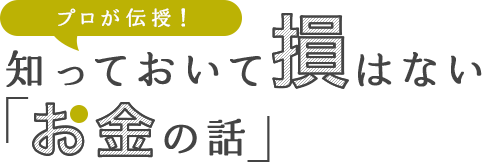コラムVol.196 マネーライターの取材裏話――マネー誌に書かなかったこと&書けなかったこと 安心老後のためにDC加入者が今やっておくべきこと

- 森田 聡子 (もりた としこ)
- 早稲田大学政治経済学部卒業後、地方紙勤務を経て日経ホーム出版社、日経BPにて『日経おとなのOFF』編集長、『日経マネー』副編集長、『日経ビジネス』副編集長などを歴任。2019年に独立後は書籍や雑誌、ウェブサイトなどで、幅広い年代層のマネー初心者に対し、難しい投資・税金・保険などの話をやさしく、分かりやすく「書く」(=ライティング)、「見せる」(=編集)ことをモットーに活動している。著書に『節税のツボとドツボ』(日経BP)、編集協力に『マンガ 定年後入門』(日本経済新聞出版社)、『教科書には書いてない 相続のイロハ』(日経BP)。
退職所得控除の「5年ルール」が封印される
この連載の読者の中には、複数の制度から退職一時金を受け取る可能性のある方が多いかと思います。2025年の年金制度改革で、そうした方にとって残念な変更がありました。
退職一時金は税務上「退職所得」の扱いになり、勤務年数に応じた「退職所得控除」が受けられます。退職所得控除額は、勤務年数が20年以下では「40万円×勤務年数(最低80万円)」、20年超だと「800万円+70万円×(勤務年数−20)」の数式で算出します。
たとえば、企業型確定拠出年金(DC)を一時金で受給し、その後に退職金を受け取る場合、間に約5年を挟めば、両方とも先の退職所得控除を満額使うことができました。これが、退職所得控除の「5年ルール」です。
しかし、変更後は約10年を空けないと退職金受け取りの際に退職所得控除をフルに活用できなくなり、手取りが減ってしまいます。実質的な「5年ルール」の封印です。
変更を受けて、今後は受給方法や受給期間を最適化するための対策が、より求められることになりそうです。
勤務先に“未知の”企業年金がある可能性
老後資金2000万円不足問題が話題になったこともあり、老後が不安だからとiDeCo(個人型確定拠出年金)や、NISA(少額投資非課税制度)の「つみたて投資枠」などを使って将来に備えているという話をよく聞きます。一方で、「そもそも、老後に向けて国や会社からどれくらいの退職金や年金がもらえる予定ですか?」と尋ねると、「う〜ん、それはよく分からない」という方が多いようです。
国の年金(老齢基礎年金や老齢厚生年金)の金額は日本年金機構の「ねんきんネット」や、毎年の誕生月に送付される「ねんきん定期便」で把握できますが、退職金や企業年金については、会社の退職準備セミナーやDCセミナーに参加して初めて知る人が少なくないのではないでしょうか。
会社によってはDC以外にも企業年金制度が用意されていますから、一度、しっかり確認することをお勧めします。
退職金と年金の受け取りをスケジューリング
企業年金制度を確認したら、自分が受け取れる退職金や年金をすべてリストアップし、受給予定期間と金額の一覧表を作成してみてはいかがでしょうか。言わば、退職金と年金の受給プランです。
リストアップの対象になるのは、公的年金(老齢基礎年金や老齢厚生年金)、退職金、確定給付型企業年金(DB)、DC、さらに私的年金としてiDeCo、NISA、民間の個人年金保険などです。
DBは第1年金、第2年金といった形で終身年金と有期年金に分かれている会社が多いようです(基本、一時金、一時金+年金の受給も可能です)。
まずは、一時金・年金選択型の制度については受給方法を決めた上で、一時金なら何歳の時、年金なら何歳から何歳までというスケジュールを引いてみるわけです。
DBの有期年金やDC・iDeCo、さらに有期型の個人年金保険は、基本的には受給期間が決まっていますから、その範囲内で予定を立てていきます。年金の種類が多いと“パズル”状態になるかもしれません。
年金を手厚くすると税金や社会保険料負担が増加
そもそも、一時金か年金受け取りかを決められないという方もいることでしょう。
確かに、従来は冒頭でお話しした退職所得控除の関係で、一時金で受け取る方が有利という風潮がありました。しかし、先の「5年ルール」の封印や、今後、退職所得控除が見直される可能性が高いことを考えると、一概に一時金が有利とは言えない状況になっています。
一方、年金受け取りにもデメリットはあります。財政赤字の日本では税金や社会保険料が高く、2025年度には国民負担率(国民所得に対する税金と社会保険料の割合)が46.2%に達する見込みです。日本の所得税は累進課税ですから所得が増えるほど税率が上がっていきますし、近年は収入の多い高齢者の医療費や介護保険の負担が重くなる傾向にあります。
従って、完全リタイアの65歳から健康寿命の75歳前後までに年金の受け取りを集中させるといったやり方は得策でないように思います。
定年時には住宅ローンを一括完済したいけれど、会社の退職金だけでは心もとないという方は一時金を増やすなど、ご自身や家庭の懐事情に合わせた受け取り方を設定した上で、税金や社会保険料などの軽減を図っていくのが妥当ではないでしょうか。
65歳未満の公的年金等控除を使わない手はない
そうした中で着目したいのが公的年金等控除です。
年金収入は丸々課税されるわけではなく、受給額に応じた控除が受けられます。それが公的年金等控除です。
公的年金の受給開始年齢となる65歳からだと110万円(年金収入が330万円未満の場合)となり、受け取る年金額が「公的年金等控除+基礎控除」の範囲内であれば課税されません。所得税を例に取ると、2025年は基礎控除が48万円から58万円に拡大され、所得が一定以下だと最大37万円の特例加算もあるため、年金収入205万円未満の人は源泉徴収されません。
公的年金等控除は65歳未満でも受けられ、控除は60万円(年金収入が130万円未満の場合)となっています。しかし、60代前半は再雇用や継続雇用で働いている人が多く、この控除枠はほとんど活用されていないのが実状です。ちなみに、65歳未満の場合は、2025年の年金収入が155万円未満であれば所得税の源泉徴収の対象にならないのです。
DB、DC、iDeCo、個人年金保険など60歳からの受け取りが可能な制度なら、「公的年金等控除+基礎控除」の範囲内で早めに受給しておくのも1つの方法でしょう。すぐに使う予定がなければ、その分を非課税のNISA口座で運用しながら長寿リスクに備えることもできます。
老後資金が潤沢だったら“今”にお金を使う
国や会社からもらえる退職金や年金を“棚卸し”したら、「意外に老後資金が潤沢なことが分かった」というラッキーな方もいるかもしれません。
あなたがそうだとしたら、将来のための蓄財は小休止して、その分を“今しかできないこと”に回してはいかがでしょうか?
自己研鑽や新しい習い事を始めることが、キャリアアップや生涯の趣味につながる可能性もあります。マイホームの購入を考えている方なら、月々の返済額に充当することでワンランク上のエリアや物件が射程圏内に入ってくるかもしれません(とはいえ、過度なローン依存にはご注意ください)。
受給プランの作成はなかなか面倒ではありますが、経験者の筆者から言わせていただくと、“入ってくるお金”の計画を立てるのは楽しい作業ですし、何より、将来が“見える化”されていくことで大きな安心が得られます。
シルバーウィークなど、時間の取れるタイミングでぜひチャレンジしていただけたらと思います。