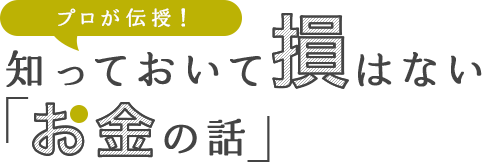コラムVol.89 地方クリエイターの仕事とお金の話11「ローカルとグローバル」

- 平川らいあん (ひらかわらいあん)
- ゲームクリエイター、シナリオライター。大手ゲーム会社でゲームディレクションを多数手がけ、その後独立。株式会社Megg(ミグ)代表取締役。独立後は複数の会社のゲーム開発に携わる。専門学校にて企画シナリオ講師やゲームを題材とした小説の執筆も行う。「お金の、育て方」内で配信中の「信託クエスト」のシナリオを担当。著書に「ゲームシナリオの教科書 ぼくらのゲームの作り方」、「ゲームプランとデザインの教科書 ぼくらのゲームの作り方」(ともに共著・秀和システム)がある。
地方で違和感
ゲームクリエイターの平川らいあんです。2017年に20年過ごした東京から地元、九州の宮崎県宮崎市にUターンしました。地方クリエイターとなった私が地方での仕事とお金のお話しをさせていただいております。今回で第11回目。
今回は、私が約2年間で気付いたことをお話しします。宮崎にUターンしてきてからずっと違和感があったのです。しかし、その違和感に中々気が付きませんでした。
違和感は、宮崎のお店やイベントのSNSでの告知を見ている時に感じていました。謎が解けたのは、市街地でゲームイベントを開催させていただいた時でした。告知する側に立った時にその謎が分かったのです。
地方でビジネスをしたいと考えている方。特にイベントをやりたいと思っている方には、興味深いと思います。ぜひ参考にしてください。
違和感の正体
違和感があったイベントの告知はこんな感じでした。あくまでも例ですので、内容は創作で名前も仮名です。
「商店街で黒木さんが主催する焼酎イベントがあります。黒木さんもいますので、ぜひ来てくださいね」
「宮崎市の中心地でゲームイベントが開催されます。三田さんが実行委員長です」
知り合いに向けての告知に見えませんか?これが公式な情報として一般の方へ向けて発信されていました。ちなみにこの黒木さんも三田さんも著名人ではなくイベントに関わっている人が知っているぐらいの知名度です。このように「イベントで何をするのか」よりも「誰がやってる」「誰がいる」というものが多いのです。
イベントの内容を知っていることが前提で、さらに「主催する人」や「関わっている人」を知っていることが前提になっています。これは全国に向けての「グローバル」への告知ではなく、地元の知っている人たちへ向けての「ローカル」への告知だったのです。違和感の正体は、告知を伝える範囲が違うということでした。
グローバルとローカル
私はゲームの仕事をずっと続けてきたので、告知は日本の全体に向けて、場合によっては世界に向けての「グローバル」へが当たり前でした。また、市街地でゲームイベントをやった時には、地元の人はもちろんですが、ゆくゆくは全国的なイベントにしたいという思いがありました。
徳島県徳島市の「マチ★アソビ」や岐阜県岐阜市の「ぜんため(全国エンタメまつり)」のようにゲームやアニメなどのサブカルイベントで全国から注目され、足を運んでもらえるものを目指していたのですが、告知は、「誰がいる」「自分がいる」というローカルへの告知がほとんどで、全国には届きませんでした。
確かにお店やイベントだとまずは地元の人に告知をして、とにかく来てもらう、手に取ってもらうことが大切だと思います。しかし、地元以上の広がりは期待できません。また「人」を推した告知だと、知らない人は行ってはいけないような感覚になってしまいます。内輪感が強くなり、閉鎖的なコミュニティになる恐れもあります。
参考までに宮崎県に訪れている観光者数を見てみました。観光庁「宿泊旅行統計調査」から全国の「延べ宿泊者数」(2019年)をみてみると、宮崎県は「37位」となっています。これは宿泊した数の総数なので、ビジネスでの宿泊数も入っていますが、観光者だけだとしても順位は大きく変わらないだろうと推測できます。
また、海外を含む県外からどれだけの人が訪れているかの指数として、「延べ宿泊者数」の「都道府県外からの宿泊者数の割合」でみてみると、宮崎県は「43位」となっています。

このように宮崎は、県外から来ている人が非常に少ないのです。宮崎はいい所や食べ物が美味しいお店がいっぱいあります。できれば全国に広がり、もっと宮崎に来てほしいし、発展してほしい。そのためには「グローバルとローカル」の視点を持ってビジネスをし、プロモーションをしていく必要があるのでないかと感じています。