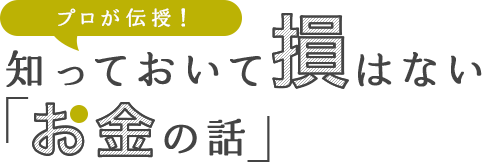コラムVol.24 「趣味としての投資」と「仕事としての運用」

- 神戸 孝 (かんべ たかし)
- 早稲田大学法学部卒業。1980年、(株)三菱銀行入行、イマジニア(株)の設立に参画後、1987年日興證券(株)入社。以後一貫してFPサービスを中心とするマーケティング手法の企画・開発に携わる。各種マーケティング用ツール及びシステム開発、商品開発、各種講演会・研修会講師、新聞・雑誌等へのFP関連記事執筆等により、資産運用に強いFPとしての評価を確立する。
1999年、日興證券(株)を退社後、FPアソシエイツ&コンサルティング(株)を設立。独立系FPとして自ら個人・法人等のコンサルティング、各種講演会・研修会講師などを行う傍ら、全国の独立系FPのための支援ビジネスも展開している。
2つの運用スタイル
投資や運用と聞くと、ハラハラ・ドキドキがつきものだと考えられがちですが、実は資産運用には大きく分けて、ドキドキも楽しむ「趣味としての投資」と、あまり面白味はないがじっくり資産を育てる「仕事としての運用」の2つのスタイルがあります。
| 趣味としての投資 | 仕事としての運用 | |
|---|---|---|
| ニーズ | 投資を楽しみたい、儲けたい | お金にある程度働いてもらいたい |
| 必要なもの | 相場観、タイミング | 投資観 |
| 投資スタイル | 短期・中期・長期、集中投資 (リスク・テイク) |
長期国際分散投資、積立投資 (リスク・コントロール) |
| 特徴 | 面白い、ドキトキ感あり | 面白くない、退屈、面倒 |
| 候補となる商品 | 個別株、テーマ型投信、FX、ブル・ベア型投信(注) | バランス型投信、投信を組み合わせたポートフォリオ運用(ファンド・ラップ等) |
| ポイント | 「売り」のルールを持つこと | 続けること |
| ふさわしい制度・口座 | NISA(成長投資枠)、特定口座 | NISA(つみたて投資枠)、iDeCo(個人型確定拠出年金) |
- (注) 「ブル」は牡牛が角を突き上げる仕草から「相場上昇」を指し、「ベア」は熊が前足を振り下ろす仕草から「相場下落」を指している。「ブル型」は相場が上昇するとき、「ベア型」は相場が下落するときに利益がでる仕組みとなっており、相場見通しに基づいて投資を行う。
趣味としての投資
「趣味としての投資」は、ドキドキ感を楽しみながら儲けることを目的として行う、おそらく多くの皆さんが、これが「投資」だと考えているイメージの運用スタイルです。有望な商品を選び出し、タイミングを見計らって買い、そこそこ値上がりしたら売却をして利益を得る(「安く買って、高く売る」)といった行為を繰り返します。
値上がり益を期待して売買を行うこの運用スタイルでは、価格のブレ(リスク)を狙うことになります。「勢いのある企業の株式や金融商品を買って急騰したときに売る(短期)」、「価格が割安な時期に買って割高な水準になったら売る(中期)」、「新興企業の株式を買って将来大きく成長したときに売る(長期)」など、いくつかのスタンスがありますが、リスクをとって(価格が上ブレることを期待して)、特定の投資対象に集中して投資を行うのが一般的です。そのため、特に短期売買のスタンスで利用されることが多いFXやブル・ベア型の投資信託までは利用しない人でも、テーマ型の投資信託や個別株などを投資対象の候補にする場合が多いでしょう。
一般的に趣味にはお金がかかりますから、この運用スタイルでは損失が発生しても、趣味にかかった費用と考えるべきで、失っても耐えられる余裕資金で行うのが基本です。この「趣味としての投資」を行っている人は、日本人の場合、10人のうち2人程度しかいないと言われています。
仕事としての運用
一方、将来のライフプランの実現のために、これから資産を形成していきたいというニーズに対しては、お金に働いてもらう「仕事としての運用」のスタイルが適しています。このスタイルではお金が働きやすい環境を整える労務管理のような作業が求められるため、どちらかと言えば退屈で面白味のない運用といえます。相場観などは必要とされないため、ほとんどの人が行えるはずです。
仕事としての運用で最も重要なのが、価格のブレ(リスク)を抑えることです。長期で資産形成を行う場合、値動きが大きな運用ではせっかくの複利効果がマイナスに働いてしまいかねないからです。値動きを抑えるには、国内外の株式や債券、不動産などの値動きが異なる資産に分散して投資を行うポートフォリオ運用が適しています。(当コラムVol.11「分散投資とは?投資の王道でリスクをコントロール」ご参照)
また、商品の分散だけではなく、購入時期の分散も重要です。最近では投資信託などを毎月少額ずつ購入して積み立てていくこと(積立投資)ができる金融機関が増えています。定額の積立投資を続けると、価格が高い時には少量を、安い時にはより多く購入することになり、結果的に平均購入価格を抑える効果が期待できます。(当コラムVol.1「資産作りの王道は積立投資!」ご参照)
このように投資する商品や時期の分散を行うことで、リスク(ブレ)をコントロールしていくのが「仕事としての運用」の最大の特徴です。この運用スタイルでは、資産配分が崩れたときに元の比率に戻すリバランスという面倒な作業も重要になりますが、商品内でリバランスが行われる仕組みのバランス型ファンドやファンド・ラップなどを活用すれば、その作業も専門家に任せることができます。
なお、それぞれの運用スタイルによって活用すべき制度も異なります。「趣味としての投資」ならば、タイミングを見計らいながら個別株のまとめ買いも可能なNISA(成長投資枠)が候補となるでしょうが、将来のライフプランの実現に向けて、「仕事としての運用」を行いたいなら、積立での長期運用が前提といえる、NISA(つみたて投資枠)やiDeCo(個人型確定拠出年金)を活用すべきです。
すでに投資を行っている方は、自分が現在行っている投資はどちらのスタイルなのか、それは自分の目的に合ったものなのか、を確認してみてはいかがでしょうか。